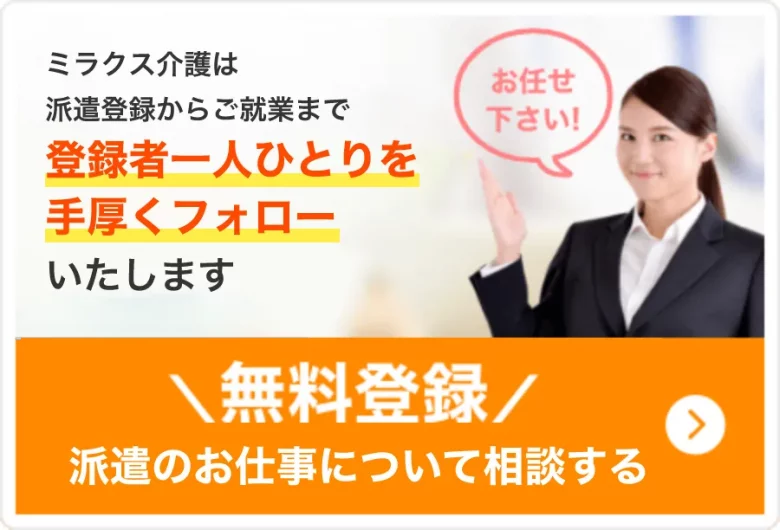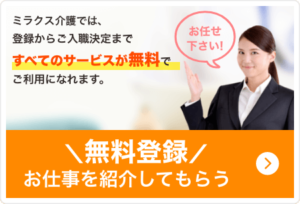「ケアマネージメントってどんな意味があるの?」「具体的な事例が知りたい」このような疑問を持つ方も少なくないのではないでしょうか。ケアマネージメントとは、支援や介護が必要な方のニーズや課題に対し、サービスを提供するプロセスあるいはシステムのことです。
本記事では、ケアマネージメントのプロセスや実際にあった事例を中心に解説します。
ケアマネージメントとは?
支援や介護が必要な方であっても住み慣れた地域で自立した生活が送れるように、適切なサービスを利用したり利用者の能力を引き出したりする必要があります。利用者が置かれている状況の課題を把握したうえで、適切にサービスを調整する技法をケアマネージメントと呼びます。
利用者が持っている能力に応じた日常生活を送ることを求めていれば、「人間の尊厳」にもとづき「自己決定」や「自立」の権利を持っています。利用者が希望や意思を実現するには、ケアマネージメントのプロセスとシステムが欠かせないといえるでしょう。
続いて、ケアマネージメントの目的について解説します。
ケアマネージメントの目的
ケアマネージメントは、利用者の「自己決定」や「自立」を支えることにより「人間の尊厳」を守ることを目的としています。支援を必要としている方とその家族が、住み慣れた地域で自立して生活できるようにケアーマネジメントし、サポートするのです。
続いて、ケアマネージメントの中心的役割を担うケアマネージャーについて解説します。
ケアマネージャー(介護支援専門員)の役割
要支援者や要介護者のケアマネージメントの中心となるのは、ケアマネージャー(介護支援専門員)です。
利用者が生活を営むうえで、医療や福祉をはじめとした多様なサービスを適切に利用する必要があります。それぞれのサービスを提供する専門職がチームとなって利用者を支援するには、サービス提供者事業間の協力や調整が欠かせません。
そこで、利用者の生活全体を総合的に捉えたうえで、課題を解決できるようにサービスを調整する役割が必要となります。その役割の中心となるのがケアマネージャーです。
ケアマネージャーは、介護保険法によって規定された専門職です。ケアマネージャーになるには、受験資格を満たしたうえで介護支援専門員実務研修受講試験に合格しなければなりません。試験に合格し、都道府県知事から介護支援専門員証を交付されれば、ケアマネージャーとして働くことができるのです。
続いて、ケアマネージメントの6つのプロセスについて解説します。
ケアマネージメントの6つのプロセス
ケアマネージメントを行うには、利用者のニーズや課題を明確にしたうえで解決に導かなければなりません。そのなかで活用される6つのプロセスについて解説します。
インテーク
インテークでは、相談内容がケアマネージメントの対象であるかを確認し、利用者のニーズや課題を整理します。
インテークでは、次の内容について確認しましょう。
・その時点のおもな相談内容
・守秘義務
・ケアマネージメントの内容と目的
・ケアマネージャーと利用者の役割と責任
・納得と同意にもとづいて進めること
ケアマネージャーと利用者が初めて対面するため、人間関係を印象付ける大切なプロセスであるといえるでしょう。
アセスメント
アセスメントでは、利用者が自立した生活を目指すにあたって課題やニーズなどの情報を生理します。日常生活動作(ADL)や居住環境などの情報収集を行い、利用者が望む生活を妨げている原因や自立に向けて利用者がどのような希望を持っているかを明らかにします。
解決するべき課題を明確にして、ケアプランに反映させるのです。
スケアプラン
アセスメントで収集した情報をもとにケアプランを作成します。ケアマネージャーが中心となって作成しますが、利用者やサービス提供事業者などの協力も欠かせません。利用者をはじめとしたすべての人が自立支援に対する共通の意識を持つことで、それぞれの役割を明確にできるでしょう。ケアプランがサービス担当者会議の場で了承された場合、契約を締結します。
ケアプランの実施・管理
ケアプランが了承されたら、それぞれのサービス提供事業者と利用者が契約を締結します。そして、ケアプランが実施されるなかでも不都合が生じていないか、新たな課題が生じていないかなどを確認するのもケアマネージメントの一環です。不都合などがあれば調整し、必要に応じてサービス提供事業者と連携する必要があります。
モニタリング・再アセスメント
モニタリングでは、ケアプランが利用者の実情に合っているかを評価します。ケアプランで定めた目標が達成できているかを確認し、達成できていなければその原因を分析するのです。ケアマネージャーだけでは利用者の実情を判断しきれません。そのため、サービス提供事業者などと連携し、情報を収集してモニタリングに役立てます。
終結
利用者の死亡や施設への入所、自立などが理由でケアプランによるサービス提供が必要なくなると、ケアマネージメントが終結します。
続いて、ケアマネージメントの具体的な事例をご紹介します。
ケアマネージメントの事例
ケアマネージメントは6つのプロセスにもとづいて展開しますが、なかには支援が難しい困難事例も存在します。ケースごとに個別に判断するためにも、ケアマネージメントの質の向上が求められるでしょう。
実際にあった困難事例と、それぞれの支援のポイントについてご紹介します。
事例①ターミナル期で複雑な感情を抱えている老々介護のケース
医師から末期がんとの告知を夫が受け、入院したのちに本人の希望によって在宅で生活することとなりました。ターミナル期ということもあり、本人も精神状態が落ち着かない状態です。これまで妻が介護をしてきましたが、心身ともに追い詰められている状況です。
妻より相談を受けて訪問しましたが、ターミナル期の複雑な感情があるため、サービス開始に苦慮しています。
担当したケアマネージャーの考えと取り組み
・本人の精神状態とサービス導入時期の見極めが重要
・介護者である妻に対するフォローが必要(心身の負担の軽減)
・ターミナル期の複雑な感情の変化に配慮しながら、サービス導入を勧める
・自宅で安心して過ごせるように、環境整備とともに急変時に対応できる体制の構築
この事例から学べるポイント
・在宅における担当医師へ協力を依頼
・どのような支援ができるのかを妻と本人に情報提供し、ともに検討する
・本人の精神状態や体調を考慮したうえで、サービス導入の時期を検討する
・入院中に行えなかった話し合いは、在宅に戻ってから補う
・介護者支援のため、介護者の話を聞く機会を多く持ち、精神的なフォローを心掛ける
事例②家族のサービス拒否によってサービス継続が難しいケース
本人と介護者である妻とは口論が絶えない状況であり、日常生活にも支障をきたしています。妻は、その様子から認知症の可能性も考えられ、長男夫婦も心配になり時々訪れますが、妻になかなか家の中に入れてもらえません。本人・妻・長男の嫁にヒアリングをしたところ、主張にそれぞれ違いがありました。そのため、本人へのサービスをどう導入したらよいか戸惑っている状況です。
担当したケアマネージャーの考えと取り組み
・冷静さを失っている長男の嫁からの相談で支援を開始したが、嫁の主張と現実に大きな食い違いがあった
・本人も初めは混乱していたが、サービス受け入れに納得する。しかし、その後も妻の激しい拒否によってサービスは継続できず、中断を繰り返す。妻が納得するサービスを模索する
・本人と妻の仲が悪く、訪問時は怒鳴り合いの喧嘩になってしまい、仲裁に入るのが大変な状況
・家族の意見がそれぞれ異なり、キーパーソンが誰なのか当初は困惑することがあったため、家族会議を提案してキーパーソンを決定してもらう
・家族関係の調整に時間をかけずに、本人に目を向けた介護を心掛ける
この事例から学べるポイント
・サービスがなくても毎月訪問し、ケアマネージャーはサービスを勧めるだけの人ではないと理解してもらい、相談へつなげる。
・常に本人の立場に立ち、本人にとって必要なサービスについて考えることを心掛ける。
・キーパーソンを決める際は家族での話し合いの機会を持ってもらう。
・サービスは、拒否的な妻のことも視野に入れて導入の工夫をする。
まとめ
介護が必要な状態であっても、自己決定や自立の権利を持っています。その基本的な権利を守るためには、ケアマネージメントは欠かせないといえるでしょう。ケアマネージメントと具体的な事例について知識を深め、利用者の生活を支えるのに役立てましょう。