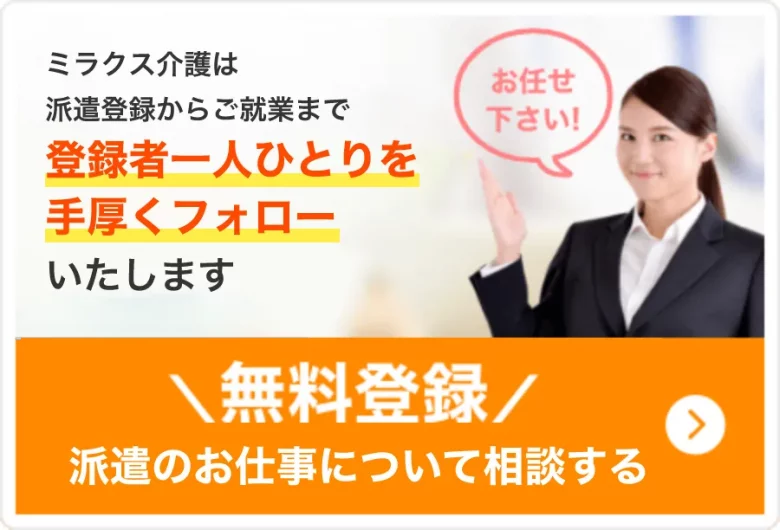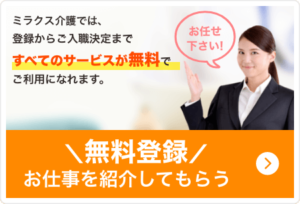義肢装具士という名前を耳にしたことはあっても、仕事内容がイメージしづらい方もいるのではないでしょうか。
義肢装具士は身体の一部を失った方などが使用する義肢装具の製作や、装着部位の型どり・採寸・身体への適合を行う仕事です。義肢装具士養成施設に通ったのちに試験に合格し、国家資格を取得しなければなりません。
本記事では、義肢装具士の仕事内容や向いている人の特徴を中心に解説します。
義肢装具士について理解を深め、仕事の選択肢の1つに加えてみてはいかがでしょうか。
義肢装具士とは
義肢装具士は英語で「Prosthetist and Orthotist」と呼ばれ、POと略されます。身体の一部を失った方や、身体の機能の一部を失った方が使用する義肢装具の製作などが仕事です。患部に負担が掛からないようにそれぞれの状態に合わせるため、装着部位の型どり・採寸・身体への適合なども行います。
義肢装具の活用によって身体に障害がある方の活動範囲は広がります。患者様の持っている能力を活かせるため、QOL(生活の質)の向上にも役立つでしょう。
仕事内容
義肢装具士の具体的な仕事内容は以下の通りです。
・障害の部位の状態を観察したうえで、装着部位の採寸や型取りを行う
・障害の部位・体格などを考慮したうえで、素材・構造・パーツを選んで義肢などを設計する
・義肢などを患者様の身体に合わせて調整し、医師によるチェックを受ける
・病院や個別の患者様などから相談を受ける
義肢装具は医師の処方にもとづいて製作します。患者様はもちろんのこと、医師やほかの医療従事者ともコミュニケーションを取って情報収集します。得られた情報・医学知識・製作技術をもとに、それぞれの患者様に適した義肢装具を製作するのです。
また、義肢装具は金属・プラスチック・皮革・繊維材料などの多種多様な材料から作られています。これらの材料の加工には、大型の工作機械や手工具を扱える技術も必要です。
近年では既製品化されているパーツも利用しますが、不具合があれば義肢装具士が調整します。そのため、臨機応変に対応できる技術力も求められるでしょう。
おもな勤務先
義肢装具士が活躍している場は以下の通りです。
・義肢装具製作所
・病院
・リハビリテーション施設
日本義肢協会に所属している義肢装具製作所は、全国に約300事業所あります。義肢装具士はこのような義肢装具製作所に勤務するのが一般的です。義肢装具製作所は病院などと契約・提携し、患者様から相談を受けて義肢装具を製作します。
規模の大きい病院では「義肢室」を設け、義肢装具士が常駐して働いている場合もあります。義肢などを使用する患者様は、病院で治療やリハビリをしながら調整も受けられるでしょう。
リハビリテーション施設も勤務先の1つです。義肢などを使用しながら日常生活復帰に向けたリハビリを行う場合、細やかな調整が必要です。そのためリハビリ施設では、理学療法士や作業療法士などと連携しながらリハビリを進めます。
社会の高齢化などによりリハビリの需要は高まっています。そのため、義肢装具士を直接雇用する施設は増加していく可能性もあるでしょう。
続いて、義肢装具士になる方法を解説します。
義肢装具士になるには
義肢装具士になるには試験に合格し、国家資格を取得する必要があります。
義肢装具士試験の受験資格を得るためのルートは以下の3つです。
・高校卒業→義肢装具士養成学校で学ぶ(3年以上)→義肢装具士試験を受験する
・高校卒業→大学・短大・高等専門学校で所定の科目を修める→義肢装具士養成学校で規定の単位を取得する(2年以上)→義肢装具士試験を受験する
・「義肢装具製作技能士」の資格を取得する→義肢装具士養成学校で学ぶ(1年以上)→義肢装具士試験を受験する
厚生労働省が運営している職業情報提供サイト「jobtag」によると、義肢装具士が実際に働いている人が多いと感じる学歴は、最も多いのが専門学校卒で72.7%でした。次いで大卒が54.5%、高卒が22.7%、短大卒が13.6%という結果となりました。
いずれの学校を卒業しても養成学校で1年以上学ぶ必要があるため、学歴に関係なく活躍できる仕事といえるでしょう。
続いて、義肢装具士養成学校で学ぶ内容について紹介します。
義肢装具士養成学校で学ぶ内容とは
義肢装具士養成学校は全国に10校あります。3年制の養成学校で学ぶ内容の一部は以下の通りです。
・基礎科目(心理学、倫理学、物理学、外国語など)
・専門基礎分野(解剖学、人間発達学、機能解剖学、理学療法学、図学製図学など)
・専門分野(義肢装具学概論、上肢装具概論など)
・義肢装具の製作、適合のための製作技術
・義肢装具に使われる多種多様な材料に関する知識
・採寸から製作までの一連の流れの実習
・問題発生時の対処方法に関する知識 など
実際に義肢装具を使用されている方を招き、採寸から適合まで実習する学校もあります。臨床実習もあり、義肢装具製作所などで実際に義肢装具を製作します。
医学分野と工学分野の科目を学びつつ実習で義肢装具を製作することで、義肢装具士になるのに欠かせない知識と技術が習得できるでしょう。
続いて、義肢装具士に向いている人の特徴を解説します。
義肢装具士に向いている人の3つの特徴
義肢装具士に向いている人の特徴は以下の3つです。
・コミュニケーションを大切にできる
・創意工夫できる
・ものづくりが好き
それぞれ解説します。
コミュニケーションを大切にできる
人とのコミュニケーションを大切にできる方は義肢装具士に向いているといえます。
義肢装具に対して患者様が痛みや違和感を覚えた場合、コミュニケーションをとりつつ細やかに調整しなければなりません。そのため、患者様が自分の思いを話しやすい関係性や信頼関係の構築は欠かせないといえるでしょう。
また、義肢装具士はおもにリハビリテーションの分野で活躍します。リハビリテーションでは医師・看護師・理学療法士・作業療法士などの幅広い職種と連携する必要があります。そのため、コミュニケーションを大切にして必要な情報収集を欠かさない姿勢が求められるでしょう。
創意工夫できる
義肢装具士は創意工夫できる方が向いているといえるでしょう。義肢装具はある程度決められた行程で製作しますが、それぞれの患者様の状態に合わせる必要があります。そのため、柔軟に対応しなければなりません。全く同じ義肢を作ることはなく、今まで対応した経験がないケースに出会う場面もあるでしょう。そのようなケースでも創意工夫し、試行錯誤を繰り返してやりきる姿勢が大切です。
ものづくりが好き
義肢装具は多種多様な材料を使用します。材料を加工するには、大型の工作機械やかなづち、のこぎり、ドリルなどの手工具を使いこなさなければなりません。加えて、製作はほとんど手作業で行い、数ミリの違いが使い心地を左右します。そのため、ものづくりが好きで作業を丁寧にこなせる方が向いているでしょう。
まとめ
社会の高齢化などが背景となり、義肢装具士が活躍しているリハビリ分野の需要は高まっています。義肢装具士は個人に合わせた義肢装具の製作などを担い、身体に障害がある方のQOLの向上をサポートできます。
義肢装具士の仕事に関心がある方は、資格取得も視野に入れてみてはいかがでしょうか。