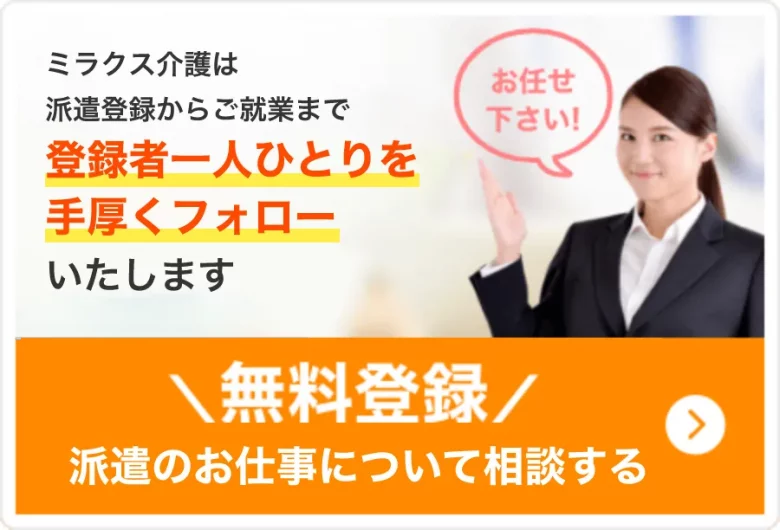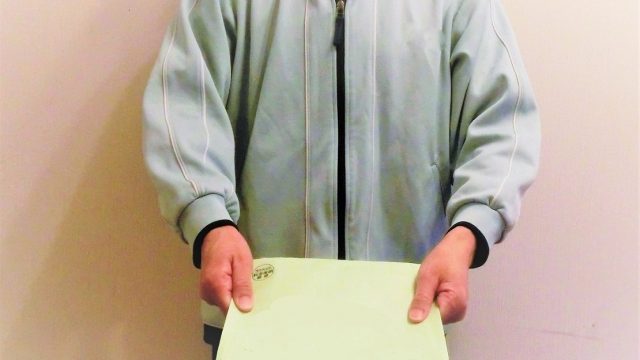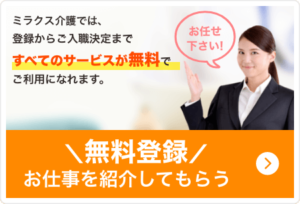エンパワメントという用語は、介護だけでなくビジネスのシーンでも一般的に使われるようになりました。それでは介護におけるエンパワメントとは、どのような意味をもつのでしょうか。今回は、介護においても重要なエンパワメントについて、その意味や成り立ち、実践方法などを解説します。介護福祉を実践するさいは、利用者さんの自立に向けて援助する姿勢が大切です。エンパワメントを理解し実践すれば、利用者さんが自立した生活を続けられるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
エンパワメントとは自分の力に気づき発揮させること
エンパワメントにはいろいろな定義があります。厚生労働省の身体障碍者ケアガイドラインでは、”社会的に不利な状況に置かれた人々の自己実現を目指しており、その人が持っているハンディキャップやマイナス面に着目して援助するのではなく、長所、力、強さに着目して援助すること”とされています。介護福祉においては、利用者さん本人や家族の強みを活かし、自分から周りの環境をよりよくしていけるように援助する行為といえるでしょう。介護職がエンパワメントを実践するにあたって重要なのは、介護者と利用者さんとの間に依存関係をつくらないことです。介護職が、介護の必要な利用者さんを指導するのではありません。介護が必要な利用者さんの持っている能力を、最大限引き出せるように援助するのです。
介護の必要な利用者さんが力を付けてきたら、徐々に距離を保って見守ります。そしてゆくゆくは、支援の必要がない状態になるのが理想でしょう。エンパワメントの実践では、なんらかの原因で自立が難しくなった人を支え、できる限り本人の力で課題を解決できるように力を高めるのが重要になります。
※参考: 厚生労働省「身体障碍者ケアガイドライン」
エンパワメントの歴史
エンパワメントという言葉は、1976年にソロモンが刊行した「黒人のエンパワメント:抑圧されている地域社会によるソーシャルワーク」で、その重要性を指摘して広まったと言われています。その背景には、アメリカ合衆国の黒人差別の歴史が関係しています。ソロモンは黒人が長年抑圧されてきたために、生きる力を失っていると考えました。そしてその状態を解消するためには、エンパワメントの実践が必要と主張したのです。その後、公民権運動だけでなく障害者の自立運動などで、権利を主張して立ち上がる動きや、福祉施設などにおける従来の「医療モデル」から「生活モデル」への脱却の動きに合わせて、エンパワメントの概念が浸透していきました。
エンパワメントとストレングスとの違い
福祉を学んだ方なら、ストレングスという用語も学んだことでしょう。よく混同されてしまうエンパワメントとストレングス。ここではストレングスについて解説します。ストレングスとは支援を必要としている人の意欲や能力、さらには希望なども含みます。ストレングスは介護福祉のケアマネジメントなどで、ケアプラン作成に重要な要素として用いられている視点です。介護における支援では、まず援助が必要な人の課題解決のために、ストレングスに着目します。そしてその次にエンパワメントして、力を加えていきます。エンパワメントとストレングスは、独立した考え方ではなく密接に関連したものなのです。
福祉施設でのエンパワメント
福祉施設では、気をつけなければ介護者と要介護者の間に主・従関係ができてしまいます。そのような特殊な施設の環境で、どうすれば利用者さんのエンパワメントができるのでしょうか。
次に、福祉施設においてエンパワメントを行う方法について解説します。
・利用者と信頼関係を築く
・仲間を作る
・組織を変える
・社会を動かす
利用者と信頼関係を築く
利用者さんのエンパワメントで最も大切なのは、介護者が利用者さんの力を信じることです。「利用者さんは課題を解決する能力がある」「利用者さんには自立できる力がある」そのように信じるのが、エンパワメント実行の第一歩となります。利用者さんを信じる気持ちがあれば、利用者さんへの接し方もおのずと違ってくるでしょう。当然ながら「できない利用者さんに変わって、自分がやってあげている」態度では、信頼関係は築けません。その人の持っている力(ストレングス)を信じ、何とか引き出そうとする姿勢が大切です。そうすれば、おのずと信頼関係が築けていくでしょう。
仲間を作る
施設において同じ課題を抱えている利用者さん同士で「共通の課題」をもち、解決に取り組むのも有効です。その効果は主に以下の3つがあげられます。
・グループで課題に取り組むことで、孤立感や孤独感から立ち直り「自分だけではない」と感じて安心感が得られる
・「支えられる側」だった自分が「相手を支える側になる」との自己効力感が得られる
・同じ境遇の利用者に支えられ「より受容されている」安心感が得られる
とはいっても、高齢者施設においては認知症の進行や、寝たきりの状態にある方々も多いでしょう。その場合は、利用者さんだけで仲間を作るのは困難です。そのため、介護職員が利用者さんの代弁者となる必要があるでしょう。利用者さんの思いを代弁するさいにも、利用者さんを「介護の必要な人」と捉えるのではなく、一人の人間としてその力を信じる態度が求められます。
組織を変える
利用者さんと信頼関係が築け、利用者さん同士もグループが作られるようになると、次は課題解決の行動に移す時期です。たとえば、介護職員は効率よく介護サービスを提供できるように、業務や施設の環境を整備します。しかし、利用者さんの視点から見ると、また違った改善点が見つかるはずです。そして介護職員は、利用者さんが主体となって改善に取り組めるように援助します。その改善を利用者主体で行うためには、職員がどのように支援するかがポイントになります。介護する側・される側ではなく、対等な立場でコミュニケーションをとる必要があるでしょう。また、利用者さんの声を集める仕組みづくりも必要になります。しかし、介護業界の人手不足は深刻なものがあります。一人ひとりの利用者さんに手厚く接するのも難しい状況です。時間的・人員的な要因で難しい場合もあるでしょう。しかし「利用者主体」は理想論と、切り捨ててはいけません。利用者さんの利益を優先する専門職としての倫理観に立って、利用者さんとしっかり向き合う態度を忘れないでください。
社会を動かす
「社会を動かす」というと大げさに聞こえます。ここでいう「社会を動かす」とは、何も政治運動するとは限りません。まずは、利用者さんの社会参加の援助から始めてみましょう。自分一人では解決できない課題を、抱えている利用者さんも多いはずです。その場合、行政などの公的機関を頼るのは、おかしくはありません。また公的な選挙などで、自分の課題を解決してくれそうな候補者に投票するのも、社会参加の一つです。そのさいに、候補者の情報を利用者さんに提供するのも、エンパワメントといえるでしょう。重要なのは、利用者さんのこのような行動に対して、職員が理解を示して情報の提供やときには相談に乗るなどのサポートをすることです。利用者さんが施設内での活動にとどまるのではなく、社会に参加し行動していくのを見通した援助を心がけましょう。
エンパワメントで利用者さんが自分の人生の主人公に!【まとめ】
エンパワメントとは、自分で自分の人生を良くしようとする行動に、さらに力を加えるよう援助する行為です。とくに施設ですごす利用者さんは社会参加の機会が少なく、自分自身の役割も見いだせなくなってしまいます。そのような状況では「自分が生きている」のではなく「生かされている」と思うようになるでしょう。「自分が誰かのおかげで生かされている」状況は、誰しも本意ではありません。そのような方々を、エンパワメントで自分の人生の主役になれるように援助するのは、介護の仕事にたずさわる人の使命といえます。実践するのはたしかに難しいものがあります。まずは、利用者さんの能力を全面的に信じて、信頼関係作りから始めましょう。