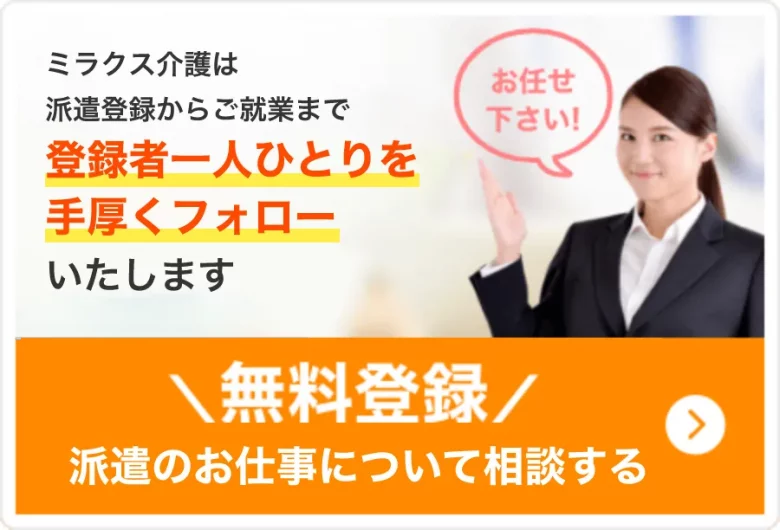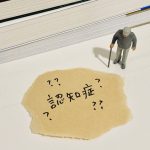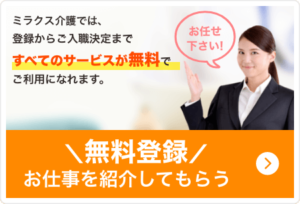介護現場では「アセスメント」という言葉をよく使います。しかし、意味合いが曖昧な方は多いのではないでしょうか。アセスメントは介護を提供する骨組みとなる大切な工程です。
今回は、介護現場におけるアセスメントの解説とアセスメントの視点やシートに記入する時のポイント5つを紹介します。
介護現場でのアセスメントとは?
福祉で使われるアセスメントとは、利用者の生活環境や困りごとを把握・情報収集し分析することです。情報を収集して整理しないと、ケアの統一ができず質の高い介護が提供できません。また、アセスメントの意味は「現状を把握」「困りごとを明確にする」「意向や希望を明確にする」3つあります。
利用者やご家族が「何に対して困っているのか」「何を希望してきるのか」「本当に必要なサービスは何か」をきちんとアセスメントし、分析することで良質な介護の提供に繋がります。一般的に、ケアマネジャーがケアプランを作成する時にアセスメントを行いますが、介護職員が計画書を作成する際に行う場合もあります。なので介護現場で働く上で、アセスメントを知っておくと安心です。
次の章では、アセスメントする時に大切にしておきたいポイントを解説します。
アセスメントする時の視点
アセスメントを行う時に大事にしておきたいポイントは5つあります。
1.事前にある情報は整理して準備しておく
2.現在の利用者の状態を理解する
3.できること・できないことを把握する
4.利用者やご家族の要望や目標を聞く
5.専門職のヒアリングして他職種とも考える
アセスメントは、ケアマネジャーが初回訪問時や介護サービスを初めて利用する際に行うことが多いです。初めての情報収集は時間が掛かるので、ある程度ポイントを押さえておくとお互いの負担が軽減できます。では、それぞれの内容を具体的に紹介します。
事前にある情報は整理して準備しておく
利用者の生活環境や身体状況を事前に情報を整理することで、適切な質問ができ利用者やご家族の困りごとや要望が引き出しやすくなります。ケアマネがアセスメントを行う場合は、関連機関から、利用者の基本情報や生活歴、病歴、家族構成などの情報があるので、事前にまとめ整理しておくことが大切です。
現在の利用者の状況を理解する
利用者の身体面・認知面・精神面・社会面を具体的に把握します。また、利用者さんのご家族の状況は、夫婦二人暮らしや同居家族が非協的など様々なパターンがあるので、しっかり理解しておきましょう。
できること・できないことを把握する
できること・できないことを把握して本人の意欲やADL低下を予防します。利用者の状況を把握すると、能力はあるが「してないこと」が出てきます。本人の意欲やご家族の介護のしすぎという場合もあるので、できること・できないことを把握しましょう。
利用者やご家族の要望や目標を聞く
利用者とご家族の目標や要望を聞くことで、具体的な解決方法を見出し良質な介護が提供できます。現在の状況を理解して、できることを把握して一緒に目標へ向かっていくという姿勢が大事です。
専門職にヒアリングし他職種とも考える
目標や要望を叶えるためには、多角的な意見と専門的な知識が必要です。ヒアリングを行うことで様々な視点が入るので、選択肢の幅が広がり解決方法が見出せます。
アセスメントをする時の視点のポイントを押さえたら、次はシート作成時に関する説明をします。
アセスメントシートを作成する時のポイント5つ
アセスメントシートは、利用者の状況をまとめる大事なツールです。アセスメントシートを元にケアプランや計画書の作成を行うので、情報を分かりやすく簡単にまとめる必要性があります。
また、関連機関に情報を提供する場合もあるので、誰が見ても伝わるようにシートを作成することも大切です。アセスメントシートを作成する時のポイントを5つご紹介します。
どうして出来なくなったか状況を分析する
「どうしてできなくなった」か背景を考えることで、適したサービスが見えてきます。例えば、おむつを使用しているから、トイレに行けないのではなく、おむつを使用している背景を分析しましょう。
背景を考えることでリハビリで解決できるのか、お薬で解決できるなど選択肢や解決策が見えてきます。
現在できることと出来ないことを分析する
できることと出来ないことを分析すると、利用者やご家族の目標が明確になり、意欲の向上やご家族の介護負担の軽減に繋がります。できることがあるのに、環境面や意欲面で「できない」と思っている場合もあるので、しっかり分析しましょう。
利用者やご家族のなりたい姿に近づく方法を考える
利用者やご家族のなりたい姿に近づくには、出来なくなった背景と現状の把握をすることで、具体的な方法が分かります。利用者やご家族の希望を尊重しながら一緒に考えることも大切です。
誰もがみても分かりやすく書く
主語を明確にする・5W1Hを使う・専門用語は多様しすぎないなどポイントを押さえながら記入していきましょう。「息子」ではなく、「長男」「次男」など具体的に書くと相手に伝わります。
専門職にヒアリングし他職種とも考える
客観的な視点を持つには、第三者や専門職の意見を聞くことが大事です。自分と異なる意見や新たな提案法や解決法が見つかり、気づきやヒントがたくさんあります。一人でシートを作成せずに人の意見や考えを聞くことも大切です。
次の章では、実際シートにどんな内容を記入していくのか具体的に中身を解説します。
アセスメントシートの具体的内容
アセスメントシートには「基本情報に関する項目」と「課題分析(アセスメント)に関する項目」の2つに分かれています。基本情報は、名前や家族構成、住んでいる場所や現状など利用者の情報のことです。課題分析(アセスメント)に関する項目は、病気や認知の度合い、できることなど利用者の情報をさらに深堀します。
それぞれどんな内容か具体的に見ていきましょう。
【基本的情報に関する項目】
1.基本情報
2.生活状況
3.利用者の被保険者情報
4.現在利用しているサービス状況
5.障害老人の日常生活自立度
6.認知症である老人の日常生活自立度
7.主訴
8.認定情報
利用者の年齢や名前、住所や家族構成、介護サービスや介護度など基本的な情報を8項目記入していきます。基本的情報の中で、一番大切なのが、「主訴」です。主訴とは、利用者やご家族がどのような介護や生活をしたいかという要望です。
【課題分析(アセスメント理由)】
9.課題分析理由
10.健康状態
11.ADL
12.IADL
13.認知
14.コミュニケーション能力
15.社会との関わり
16.排尿・排泄
17.褥瘡・皮膚の問題
18.口腔衛生
19.食事摂取
20.問題行動
21.住環境
22.特別な状況
利用者の動作や認知面、社会への関わりや環境面などの項目を記載します。13.14番目の項目は、一回だけの面接では、見えにくい部分なので日頃の生活状況をご家族にしっかり聞きましょう。
アセスメントシートは、厚生労働省が指定する23項目(課題分析標準項目)をクリアしていれば、独自の書式を使用できます。他にチェックしておきたい項目がある場合は、自身でシートの作成も可能です。
まとめ
今回は介護現場でのアセスメントついて解説しました。アセスメントは、利用者の困り事や状況を把握・情報を収集し分析することです。きちんと情報を収集して、整理することで良質な介護が提供できます。適切な介護サービスを提供するための大切な骨組みとなるので初回だけでなく、利用者の状態変化や退院後など、適宜行っておくことも大切です。