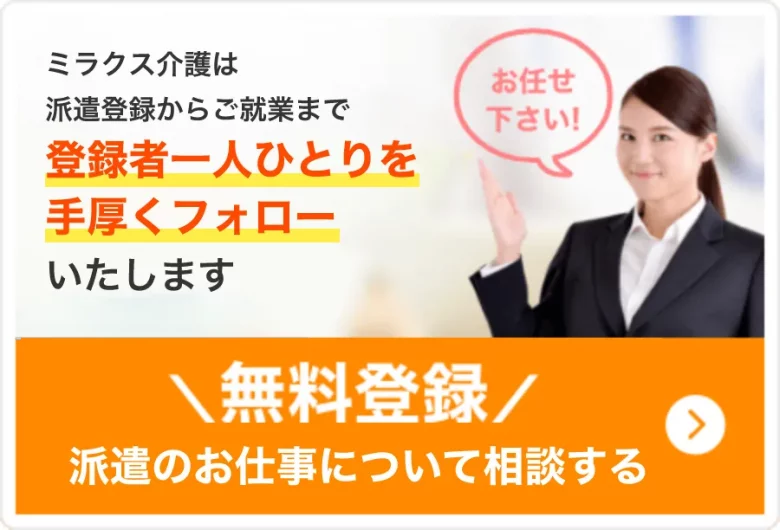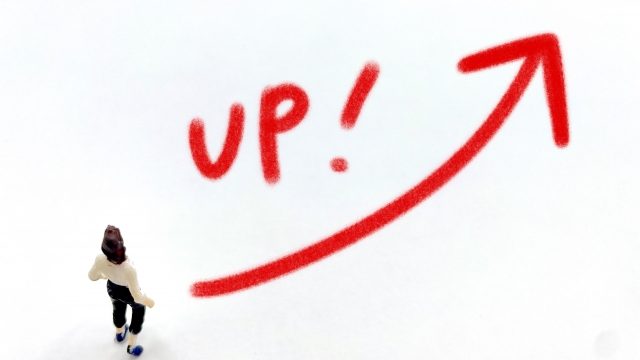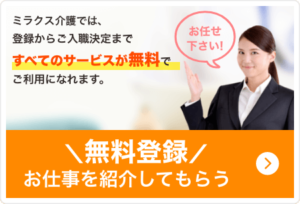相談支援専門員というお仕事をご存じですか?
相談支援専門員とは、障害のある方々の悩みを聞いて適切なサービスや制度につなげたり、地域で暮らしやすいようにサポートする専門職です。
この記事では相談支援専門員の仕事内容や就職先、相談支援専門員になるための条件について詳しく解説します。
障がい者の生活を支える相談支援専門員とは?
相談支援専門員とは、障害者が自立した生活を送れるようにサポートするお仕事です。
障害者が抱える問題は日々、複雑化&多様化しています。障害を持つ方、そのご家族は適切な情報に恵まれず、孤独に悩まれているケースもあります。障害を持つ方とそのご家族のニーズを満たすサービスや制度を紹介し、地域や社会とつなげることが相談支援員には期待されます。
※介護支援専門員と間違えないようご注意ください。
名称の似た資格として介護支援専門員があります。同じく相談業務を生業とする資格ですが、支援対象者が異なります。
・相談支援専門員:障害者の相談支援
・介護支援専門員(ケアマネージャー):高齢者の相談支援
相談支援専門員の仕事は?
相談支援専門員が対応する仕事の幅は広いです。障害者福祉全般と言っても過言ではないでしょう。
ここでは相談支援専門員の主な就業先や仕事内容についてご紹介します。
相談支援専門員の主な就業先
相談支援専門員は主に次のような就業先があります。
・基幹相談支援センター
・障害者相談支援事業所
・指定特定相談支援事業所
・指定障害児相談支援事業所
・指定一般相談支援事業所
・障害者就業・生活支援センター
・発達障害者支援センター
※参考: 厚生労働省「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要」
障害者の相談窓口としてこれらの施設はあり、利用者一人一人に合わせた対応が求められます。
相談支援専門員の主な仕事内容
相談支援専門員の仕事内容は大きく次の4つに分けられます。
※就業先によって、相談支援専門員の仕事は異なります。
基本相談支援
障害者福祉全般の問題や相談に対応する仕事です。相談支援の始まりとも言えます。初めて相談に来る利用者を対象とすることが多いため、相談内容、環境などの聞き取りから具体的な支援やサービスにつなげる大切な役目があります。
地域相談支援
地域で安心して暮らしていくためにサポートします。
具体的には次の2つの支援に分かれます。
| 地域移行支援 | 地域定着支援 | |
| 対象者 | 病院や施設を退所する人 | すでに地域で暮らす人 |
| 支援内容 | ・住居の確保 ・地域で暮らしていくための相談 ・障害福祉サービス事業所への同行 | ・24時間の連絡体制 ・緊急時対応 |
計画相談支援
障害福祉サービスを受けるためにはサービス等利用計画が必要になります。計画相談支援は支援のタイミングによって次の2つに分けられます。
| サービス利用支援 | 継続サービス利用支援 | |
| 対象者 | これからサービスを利用する人 | すでにサービスを利用している人 |
| 支援内容 | ・サービスを利用するまでのサポート ・サービス等利用計画の作成 | ・1~3か月に一度のモニタリング調査 ・関係機関との連絡調整 |
障害児相談支援
児童発達支援センターや放課後等デイサービスの利用を希望する障害児とそのご家族に対してサービスの利用をサポートします。
| 障害児支援利用援助 | 継続障害児支援利用援助 | |
| 対象者 | これからサービスを利用する児童 | すでにサービスを利用している児童 |
| 支援内容 | ・サービスを利用するまでのサポート ・サービス等利用計画の作成 | ・1~3か月に一度のモニタリング調査 ・関係機関との連絡調整 |
相談支援専門員の待遇
相談支援専門員を目指している方なら待遇は気になる部分ですよね。
ここでは相談支援専門員の勤務形態と給料についてご紹介します。
相談支援専門員の勤務
相談支援がメインとなるため、勤務形態として日勤が多いようです。介護関連の仕事では夜勤がある仕事も少なくないので、夜勤に抵抗がある方でも安心です。
相談支援専門員の給料
勤務する職場によっても給料は異なりますが、相談支援専門員の給与平均は常勤でおよそ37万円、非常勤では約24万円です。
※介護職員処遇改善加算Ⅰを届け出ている事業所で手当・ボーナス含む場合。
相談支援専門員になる方法
相談支援専門員とは資格の名称ではないため、資格試験はありません。しかし、相談支援専門員になるには相談支援従事者初任者研修という研修を修了する必要があります。
相談支援従事者初任者研修を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。職種によって必要な経験年数が異なりますのでチェックしておきましょう。
相談支援業務の経験がある方
①2006年9月30日までに通算3年以上、次の施設で相談業務に従事していて、2006年10月1日時点でも続けている方
・障がい児相談支援事業
・身体障害者相談支援事業
・知的障害者相談支援事業
・精神障害者地域生活支援センター
②次のような施設で通算5年以上、相談業務に従事している方
・障害者や障害児の相談支援事業
・児童相談所や保健所、福祉事務所などの公的な相談機関
・障害者更生施設や支援施設
・老人福祉施設、老人保健施設などの高齢者施設
・社会福祉主事などの相談業務に携わる人員のいる保健医療施設
・障害者雇用を支援する施設
・盲学校、聾学校、養護学校
介護関連業務の経験がある方
次のような施設で通算10年以上、介護の実務経験がある方
・障害者支援施設、障害者デイサービスセンター、身体障害者福祉センターなどの障害を持つ方の介護にかかわる施設
・老人福祉施設、介護老人保健施設
・障害福祉サービス事業
・保健医療機関、訪問看護事業所
有資格者の方
①通算5年以上の業務経験が必要な資格の方
・社会福祉主事任用資格者
・相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を習得した者と認められる者
・児童指導員任用資格者
・保育士
・精神障害者社会復帰指導員任用資格者
②次の国家資格に基づく仕事に5年以上従事しており、かつ相談支援業務に3年以上従事している方
・医療系資格(医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護士・歯科衛生・栄養士)
・リハビリ関連資格(理学療法士・作業療法士視能訓練士・義肢装具士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師)
・福祉系資格(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)
相談支援専門員研修の種類
相談支援従事者初任者研修
年に1~3回ほど各都道府県で実施されます。相談支援従事者初任者研修を修了しなければ相談支援専門員にはなれません。
研修と演習(グループワーク)は合計7日ほどかけて行われ、加えて各々で実習に取り組む必要があります。
研修には大きく2つの目的があります。
・障害のある方々が地域でイキイキと暮らすために、医療・介護・保健・福祉・就労・教育などのさまざまな面から支援につなぎ、サポートする方法を学ぶ。
・困難事例に対して適切な対処方法を学ぶ。
受講するには、前述したような実務経験の規定の他にも、事業所からの推薦が必要な場合もあります。各都道府県によって詳しい受講対象者やプログラムに違いがありますので、確認するようにしましょう。
相談支援従事者現任者研修
相談支援専門員を続けるには、初任者研修のみならず、5年ごとに相談支援従事者現任者研修を受ける必要があります。主にネットワーク作りや権利擁護などについて学びます。
前の研修から5年度以内に受講しない場合は、相談支援専門員の資格を失ってしまいます。資格を喪失すると、初任者研修から受けなおさないといけなくなるので注意しましょう。
初回の現任研修だけは2年間の相談支援業務の経験が必須となりますので、早めに受けておこうと考えている方もチェックしておきましょうね。
まとめ
相談支援専門員について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
相談支援専門員は障害を持つ方と地域を結ぶ大切な役割を持っています。
相談支援専門員になるには、介護や相談支援分野での実務経験に加えて研修を受ける必要があります。障害を持つ方のサポートをしたいと考えている方は、ぜひ検討してみてはどうですか?