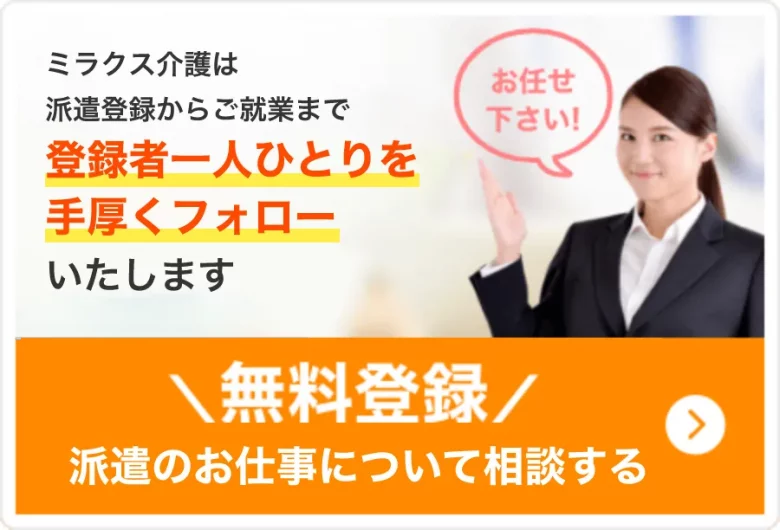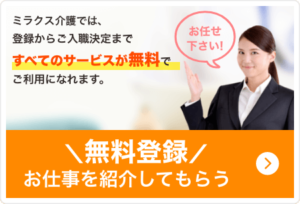加齢や疾病により寝たきり状態になると、腰や肩などの身体の一部分に体重がかかり続けます。その部位の血行が悪化すると、発疹やただれ、傷ができて褥瘡(じょくそう)が生じてしまいます。褥瘡は一度できると治りにくく、進行すると骨が露出するほどの深い傷になってしまうことも。要介護者の身体の負担や痛みを軽減するために欠かせない「褥瘡予防」についてご紹介します。
褥瘡(床ずれ)とは?
褥瘡とは、長時間寝たきり状態が続くことで起こる廃用症候群の1つで、床ずれとも言われます。長時間寝たきり状態が続くことで身体の同一部位が圧迫され、血行悪化や皮膚の壊死を起こします。
褥瘡の初期症状として見られるのは、皮膚が赤くなる「発疹」です。初期症状の段階で適切な処置や治療を行えば治癒する可能性もありますが、気づかずに放置してしまった場合、皮膚のただれや傷がどんどん悪化していきます。褥瘡が重症化すると皮膚がただれ、骨が見えてしまうくらい深い傷が生じてしまいます。褥瘡は重症化するほど治療が難しくなるため、早期発見・早期治療が必要です。
褥瘡(床ずれ)が生じる原因
褥瘡が生じるのは、単に寝たきり状態であるからというわけではありません。褥瘡が生じる原因には、以下の5つがあります。
①長時間の身体への圧迫
長時間寝たきり状態が続くことで、肩や腰、踵などの身体の一部部に体重がかかり続けます。身体の同一部位に体重がかかり続けると、その部分の血流が悪くなってしまい、発疹やただれ、傷といった褥瘡が生じてしまいます。
②皮膚の不衛生な湿潤
汗や排泄物で皮膚が不衛生に湿った状態が長時間続くと、褥瘡が生じやすくなります。また、長い期間オムツを着用していることによるただれ・かぶれも褥瘡の原因です。不衛生な状態で皮膚が湿ったままにならないよう、皮膚の清潔を保つようにしましょう。
③皮膚への摩擦
シーツや衣類がよれてシワになっていると、皮膚への負担になってしまいます。また、移乗介助やベッド上での引き上げ介助(上方移動)の際、臀部や背部に摩擦が生じると、褥瘡が発生しやすくなります。
④栄養不足
寝たきりによる身体機能の低下で食事や水分補給が困難になると、低栄養状態に陥ってしまいます。低栄養状態になることで、体重が減少し、筋肉量や脂肪量が少なくなります。体重減少に伴い、骨の突出が目立つようになり、その部分の皮膚に褥瘡が生じてしまうのです。
⑤全身の浮腫み
食事や水分の摂取量が減ることで低栄養状態となり、身体の循環が悪くなります。身体の循環が悪くなることで、全身に浮腫みが生じてしまいます。浮腫みでは皮膚の真下(皮下組織)に水が溜まった状態になるため、皮膚が傷ついて褥瘡が生じるリスクが上がってしまうのです。
褥瘡(床ずれ)ができやすい部位
褥瘡は全身どこにでも生じるのではなく、ある程度生じやすい部位が決まっています。特に、骨が出っ張った部位には長時間体重による圧力がかかり、褥瘡が生じやすくなります。また、褥瘡が発生しやすい部位は、仰臥位(仰向けで寝た姿勢)・側臥位(横向きで寝た姿勢)・座位(椅子に座った姿勢)など、長時間とる姿勢によっても異なることが特徴です。
仰臥位(仰向けで寝た姿勢)
・後頭部:かための枕を使用すると褥瘡が生じる部位
・肩甲骨部:仰向けの姿勢では上半身で1番体重がかかる部位
・脊柱部:円背(腰が曲がった状態)の場合は特に褥瘡が生じる部位
・仙骨部:全身で1場体重による圧がかかる部位
・踵骨部(かかと):末端部分で1番骨の突出がある部位
側臥位(横向きで寝た姿勢)
・耳介部(耳):かための枕の使用で皮膚や軟骨に負担がかかる部位
・肩関節部:横向きの姿勢では上半身で1番体重がかかる部位
・肘関節部(ひじ):上肢では特に関節の突出が顕著な部位
・腸骨部:骨盤の骨が突出している部位
・大転子部:大腿骨(足の骨)が突出している部位
・膝関節部(ひざ):下肢では特に関節の突出が顕著な部位
・外踵部(くるぶし):横向きの姿勢では特に骨の突出が目立つ部位
座位(椅子に座った姿勢)
・坐骨部:骨盤の底に位置する骨で、椅子の座面に当たる部位
・尾骨部:しっぽの名残と言われている骨で、椅子の座面に当たる部位
・背部:椅子の座面と汗による皮膚の湿潤で褥瘡が生じる部位
・肘関節部:車椅子のタイヤに擦れやすい部位
褥瘡(床ずれ)の予防方法
褥瘡が生じてしまってからでは、治療・治癒が難しいケースが大半です。褥瘡は生じる前に適切な対処を行うことで、予防することが可能です。
以下の5つの方法で、褥瘡の発生を予防しましょう。
①定期的に体位交換を行う
褥瘡は長時間同じ姿勢をとり続けることで、身体の一部分に圧力がかかってしまいます。同じ姿勢を長時間とり続けないために、定期的な体位交換で姿勢を変えるようにしましょう。1時間~2時間の間隔で「仰向け→横向き」「横向き→仰向け」といった感じで体位交換を行い、同じ姿勢をとり続けることを避けましょう。
②褥瘡予防用のマットレスを活用する
体圧分散マットレスやエアマットなどを活用し、身体にかかる圧力を軽減します。特に円背や体重減少により脊椎・腸骨・大転子部などの骨の突出が目立つ方には、エアマットレスの活用で身体の負担や痛みを軽減することができます。
③衣服やシーツのシワに留意する
寝たきり状態の人にとっては、衣服の縫い目やシーツのシワも皮膚の負担です。また、軽微な衣服やシーツのシワにより、褥瘡の初期症状である「発赤」が生じてしまいます。衣服の縫い目やシーツのシワが褥瘡の発生しやすい部位に当たっていないか、更衣や入浴、体位交換の際は注意して観察をするようにしましょう。
④栄養管理
身体機能の低下により、食事や水分が十分に摂れなくなると、「体重減少による骨の突出」や「浮腫み」が見られるようになります。これらは褥瘡が発生しやすい要因となってしまうため、栄養管理を徹底するようにしましょう。固形食での食事が難しい場合は、「メイバランス」「ラコール」「エンシュア」などの高機能栄養剤の飲用を勧めることも大切です。
⑤身体の清潔を保つ
汗や排泄物などで皮膚が不衛生な湿潤を起こすと、褥瘡が生じやすくなります。オムツ交換の際は陰部洗浄や清拭をしっかり行い、入浴または清拭で皮膚の清潔保持や血行促進を促すようにしましょう。
褥瘡予防のためのポジショニング
褥瘡を予防するには、定期的な体位交換やポジショニングが特に効果的です。褥瘡予防のポジショニングでは、身体の状態や姿勢に合わせてクッションを挟みます。
以下では、寝たきりの方の姿勢に合わせたポジショニングのポイントをご紹介します。
「仰向けの姿勢」のポジショニングポイント
・首:首の後ろにすき間がないよう、低反発枕やクッションを入れ込む
・肩:肩が内側に入り両肩甲骨が開くよう、肩と肩甲骨の下に薄めのクッションを入れ込む
・体幹:肩と骨盤がまっすぐになっており、ねじれや傾きがないかをチェックする
・腰:反ったり内側に曲がったりしていないかをチェックする
・膝:膝を立てた状態で、膝の裏にすき間がないようクッションを挟む
「ななめ横向きの姿勢」のポジショニングポイント
・首:首の後ろにすき間がないよう、低反発枕やクッションを入れ込む
・肩:肩が内側に入り両肩甲骨が開くよう、肩と肩甲骨の下に薄めのクッションを入れ込む
・体幹:肩と骨盤がまっすぐになっており、ねじれや傾きがないかをチェックする
・腰:骨盤がマットレスに当たらないよう、クッションを入れ込む
・両足:膝を立てた状態で、両足が平行に揃うようクッションで支える
「横向きの姿勢」のポジショニングポイント
・首:首の後ろにすき間がないよう、低反発枕やクッションを入れ込む
・肩:肩が内側に入り両肩甲骨が開くよう、肩と肩甲骨の下に薄めのクッションを入れ込む
・脇:脇の下にすき間がないよう、両手の間にクッションを入れ込む
・膝:膝を曲げた状態で、両膝の間にクッションを入れ込む
・足:左右の足先が重なっている状態で、両足の間にクッションを入れ込む左右の足が重なっている
まとめ 褥瘡予防で身体の負担や痛みの軽減を
褥瘡は重症化すると骨が見えるほどの深い傷ができ、治療にもかなりの時間を要します。そのため、褥瘡は予防することや発赤の段階で早期治療を行うことが重要です。体位交換や栄養管理、入浴や清拭によるケアで褥瘡は予防できます。また、清潔保持・血行促進を行うことで、寝たきり高齢者の身体の負担や痛みが緩和できます。