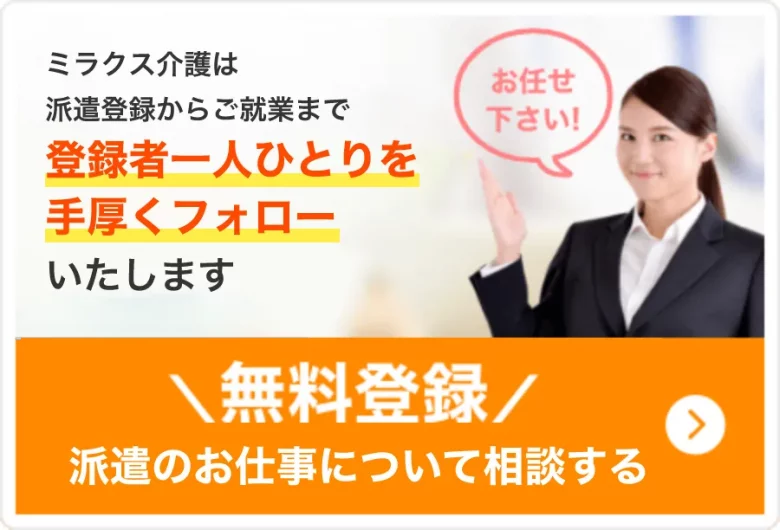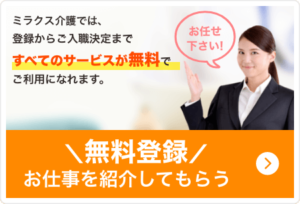要介護高齢者の生活を支える介護の仕事では、就寝介助と起床介助を日常的に行います。また、それ以外にも、離床介助や臥床介助があり、目的や手順が混ざりがちです。介護の仕事をするにあたり、それぞれの介助の目的や手順を理解しておくことが大切です。
本記事では、就寝介助と起床介助のそれぞれの違いや介助の手順について解説します。
就寝介助・起床介助とは?
介護現場で日常的に行われる「就寝介助」と「起床介助」。就寝介助と起床介助はそれぞれ、介護施設によっては「ナイトケア」「モーニングケア」と呼ばれることもあります。
それぞれの介助の内容は、以下の通りです。
就寝介助
就寝介助とは、利用者が夜、寝るための準備やケアをすることを言います。
具体的には、以下のような介助・ケアを行います。
・眠前薬の服薬介助
・就寝前のトイレ介助またはおむつ交換
・就寝前の口腔ケアや義歯洗浄
・普段着からパジャマへの着替え
・就寝前のベッドへの移乗とポジショニング
起床介助
起床介助とは、利用者が朝起きるための準備やケアをすることを言います。
具体的には、以下のような介助・ケアを行います。
・起床の声かけと車椅子への移乗介助
・パジャマから普段着への着替え
・整髪や洗顔の介助
・体調確認やバイタル測定
・起床後のトイレ介助またはおむつ交換
就寝介助と起床介助の違い
就寝介助と起床介助によく似た言葉として、「臥床介助」や「離床介助」があります。「就寝介助=臥床介助」「起床介助=離床介助」と捉えられがちですが、それぞれの介助内容や手順は大きく異なります。
ここでは、就寝介助と起床介助の違いや、さらに混同しやすい「臥床介助」「離床介助」との違いについてご紹介します。
「就寝介助」と「起床介助」の共通点と違い
就寝介助と起床介助の共通点として、排泄介助や口腔ケア、着替え介助などの日常生活に欠かせない動作の手助け・介助を行います。就寝介助と起床介助の大きな違いは、介助を行う時間帯です。
・就寝介助の時間帯:利用者の就寝時間である夕方18時~20時頃
・起床介助の時間帯:利用者の起床時間である朝6時~8時頃
就寝介助では主に、眠前薬の服薬介助やパジャマへの着替え、口腔ケアなど、寝る前の準備やケアを行うことが特徴です。起床介助では主に、起床の声かけや介助、体調確認、洗顔の介助など、1日の活動を始めるための準備やケアを行うことが特徴です。
「臥床介助」と「離床介助」との違い
臥床介助とは、利用者にベッドに横になってもらうための介助を指します。
<臥床介助の具体例>
・「車椅子に座っていたらしんどくなったから横になりたい」と言う利用者を居室に
誘導し、ベッドで横になってもらう
・おむつ交換を行うため、車椅子からベッドに移ってもらう
離床介助とは、利用者にベッドから起きてもらうための介助を指します。
<離床介助の具体例>
・食事の時間のため、ベッドから起きて車椅子に座ってもらう
・入浴介助のため、ベッドから起きて車椅子に乗り、浴室に移動してもらう
臥床介助は「休憩やおむつ交換のために一時的にベッドに横になる動作の介助」、離床介助は「食事や入浴の介助のために一時的に起きる動作の介助」です。利用者が就寝するための臥床介助は、就寝介助に含まれます。また、利用者が起床するための離床介助は起床介助に含まれます。
就寝介助の手順・介助のポイント
実際に介護現場で就寝介助を行う際、何から始めれば良いのでしょうか。ここでは、就寝介助の手順やポイントを時間軸に沿って説明します。
以下は一例のため、実際の業務内容と時間は介護施設ごとに異なります。
<17:30>
【手順】
・夕食を終えた利用者の口腔ケアや義歯洗浄
・眠前薬の服薬介助
【介助のポイント】
片麻痺がある利用者の場合、麻痺側の口腔内に食物残渣(食べ物のカス)が残っている可能性があるため、麻痺側をしっかり確認しましょう。
また、眠前薬は主治医の指示で減薬・増薬・変更になっている可能性があるため、こまめに看護師に確認することが大切です。
<18:00>
【手順】
・就寝前のトイレ介助またはおむつ交換
【介助のポイント】
数日~数週間続いている便秘により、食べた夕食が逆流したり、嘔吐したりする可能性があります。そのため、就寝介助を行う前には、排便の記録を確認しましょう。
また、食前薬・食後薬として下剤を服用している場合もあるため、日勤者や看護師に下剤の服用を確認することが大切です。
<19:00>
【手順】
・利用者の居室誘導
・普段着からパジャマへの更衣
【介助のポイント】
就寝介助を行うのは、利用者が夕食を食べた後です。逆流や嘔吐による窒息を防止するために、右側側臥位で寝てもらいます。人間の身体の構造上、右側側臥位にすることで、胃から十二指腸へと食べたものが流れやすくなります。
また、就寝介助を行う際は、利用者がゆっくり休めるよう体勢を整え、利用者の体型に合わせた適切なポジショニングを行うことが大切です。
起床介助の手順・介助のポイント
実際に介護現場で起床介助を行う際、何から始めれば良いのでしょうか。
ここでは、起床介助の手順やポイントを時間軸に沿って説明します。
以下は一例のため、実際の業務内容と時間は介護施設ごとに異なります。
<6:00>
【手順】
・起床の声かけと車椅子への移乗介助
・パジャマから普段着への着替え
【介助のポイント】
利用者は仰臥位(仰向けの状態)や側臥位(横向きの状態)で
長時間寝ており、自身で寝返りが打てない方もいます。
そのため、パジャマから普段着への着替えの際は、肩や腰、臀部などに
発赤や褥瘡(床ずれ)ができていないか確認しましょう。
<6:30>
【手順】
・整髪や洗顔の介助
・起床後のトイレ介助またはおむつ交換
【介助のポイント】
洗髪や洗顔の介助を行う際、意外と忘れがちなのが義歯の装着です。義歯がきちんと入っているか、確認し忘れないようにしましょう。
また、朝は起床介助や朝食の準備に追われがちですが、失禁を防ぐためにも排泄介助を省かずに行うことが大切です。
<7:00>
【手順】
・体調確認やバイタル測定
【介助のポイント】
起立性低血圧や意識レベルの低下など、朝は血圧やバイタルの変動が見られやすい傾向にあります。
起床介助や朝食の準備をしつつも、利用者の体調にはしっかり気を配ることが大切です。
就寝介助・起床介助の注意点
就寝介助・起床介助は、ただ単に「利用者に寝てもらう」「利用者に起きてもらう」といった介助を行うだけではありません。要介護度が高く、長時間の離床が難しい利用者の場合や、骨折や脱臼により安静が必要な
利用者の場合、様子を見ながら起床の声かけや介助を行わなければなりません。また、認知症や精神疾患による「不眠症状」が見られる利用者の場合、快適に入眠してもらうための配慮や工夫が必要になります。ここでは、利用者が快適に就寝・起床するために注意するべき点を3つご紹介します。
利用者全員に同じ対応を行わない
利用者が就寝・起床する時間帯は、介護施設ごとに決められています。例えば、19時が就寝時間と決めている介護施設もあるでしょう。しかし、利用者全員に同じ対応を行うと、眠れずに不穏になったり、徘徊したりする利用者が出てきてしまう可能性があります。
また、起床時間が一律7時と決まっていたとしても、起立性低血圧や意識レベルの低下を起こし、緊急処置が必要になる利用者が出る可能性があります。利用者全員に同じ対応を行うのではなく、利用者の体調や病状に合わせた個別ケアを行うことが非常に重要です。
寝たまま・起きたままにしない
一度就寝介助を行うと、朝目覚めが悪くて昼過ぎまで起きない。一度起床介助を行うと、徘徊してしまい夜なかなか寝付けない。このような利用者がいたとしても、寝たまま・起きたままにするのは避けましょう。就寝や起床の声かけを適宜行い、生活習慣を整えることが大切です。
環境にも配慮する
「暗いと不安になって眠れない」「明るいと気が散って眠れない」など。寝る時の照明1つにも、人それぞれのこだわりがあります。ただ就寝・起床の声かけや介助を行うだけでなく、利用者一人ひとりの希望を確認し、安心して就寝・起床できる環境を作ることが大切です。
それぞれの介助の手順・ポイントをしっかり把握しよう
就寝介助・起床介助では、それぞれ利用者の生活に欠かせない睡眠や1日の活動の始まりをサポートする役割があります。適切な介助を行うことで、利用者のQOL(生活の質)を高めることができるでしょう。就寝介助・起床介助、それぞれの介助の手順やポイントをしっかり把握し、利用者の体調や病状に適した対応を行うことが大切です。