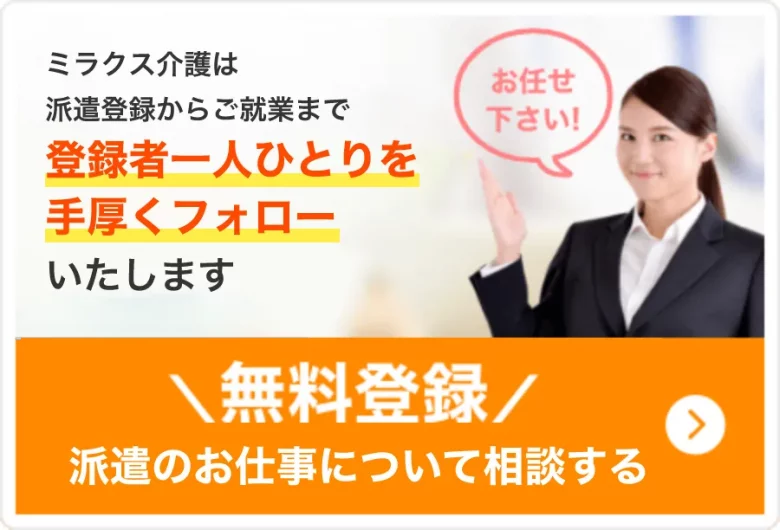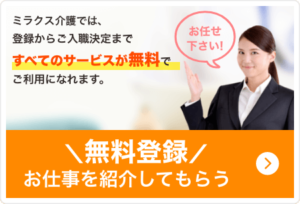「介護」と「介助」の違いは何でしょうか?
介護の現場で働く人でも「介護」と「介助」の違いがわかる人は、少ないのではないでしょうか。「なんとなく違う気がするけど、仕事には支障ないからいいのでは?」そのように考えている人も、きっと多いはずです。
しかし、使用頻度の高い用語の正しい意味を知ることは、適切な介護を提供するうえで重要です。
この記事では、介護にたずさわる方が知っておくべき基本知識として、「介護」と「介助」の違いを解説します。本記事を読めば、自信をもって「介護」「介助」を提供できるでしょう。ぜひ、最後までご覧ください。
「介護」と「介助」はどう違う?
介護の仕事では「介護」や「介助」という言葉がよく使われます。しかし、その違いをはっきりとわかる人は、案外少ないのではないでしょうか。
「介護」とは、一人で日常生活を送るのが困難な方に対して、日常生活全般を支援して自立を目指す行為を指します。そしてその自立を実現する具体的な手段として「介助」があるのです。
「介助」は具体的な、「介護」は抽象的な概念といえるでしょう。言い換えると、「介護」はその人の自立を目指す行為を指すのに対して、「介助」は介護を実現する手段であるといえます。
介護の主な内容1(身体介護)
上記にあるように、「介護」とは日常生活に支援が必要な方の活動を援助することで、自立を目指す行為を指します。「介護」に分類される主な仕事は「身体介護」と「生活援助」の2つです。以下で「介護」の主な内容を解説します。
「介護」とは?
身体介護は直接介護を必要とする方の身体に直接触れて、日常生活に必要な支援を行う方法です。身の回りの動作や、起き上がり、寝返り、立ち上がり、歩行などの基本的な生活動作の支援にわけられます。身体介護は自立支援が目的です。そのため、介護される方の出来ない部分だけを援助し、できるだけ本人の自力を活かせる支援を行うのが重要となります。
介護の主な内容2(生活援助)
生活援助とは、掃除・洗濯・調理などの日常生活の支援を指します。身体介護との違いは、介護を必要とする方の身体に直接触れるかどうかです。生活援助は、介護を必要とする方に提供されるものです。介護を必要とする方の家族への支援や、日常生活以外の支援は含まれません。
「介助」とは?
介助とは、介護を実践するうえでの手段であり、日常生活を送るのに支援が必要な方に対して、起居動作などをサポートする行為そのものを指します。介助と言っても支援を行うシチュエーションの違いにより、さまざまな種類があります。基本的な介助の内容は以下の6つです。
- 介助の内容1(食事介助)
- 介助の内容2(排泄介助
- 介助の内容3(入浴介助)
- 介助の内容4(歩行介助)
- 介助の内容5(移乗介助)
- 介助の内容6(更衣介助)
一つひとつ、見ていきましょう。
介助の内容1(食事介助)
食事介助とは、加齢や認知症、麻痺などで、食事の摂取がうまくできなくなった方の食事を支援する行為です。咀嚼機能や嚥下機能の衰え、認知症による食事への理解低下など、食事を食べない、食べられない原因を考えながら適切に介助をしていきます。
食事は、ともすれば窒息や誤嚥の原因になるため、正しい姿勢の保持が重要になります。また、介助を受ける方のペースに合わせるのも大切です。さらに、水分摂取量が低くなりがちな高齢者に対して、水分摂取の促しや摂取量の把握も忘れてはなりません。
介助の内容2(排泄介助)
排泄介助は、主に4つの介助に分かれます。
一つ目は、トイレまでの誘導と排泄前後の対応をするトイレ誘導
二つ目は、ベッドサイドなどに設置されたポータブルトイレへの誘導。
※ポータブルトイレとは、持ち運び可能なトイレのことです。歩行が不安定な方や、夜間にトイレの回数が多い方など、トイレまでの移動が困難な方のために、ベッドの近くに設置します。
3つ目は、座位が取れないなど、トイレでの排泄が困難な方へのオムツ介助
4つ目は、ベッド上で行う差し込み便器などの便器・尿器を使った介助。
それぞれ、介助を受ける方の状態に合わせて介助方法を選択します。
介助の内容3(入浴介助)
入浴介助は、身体の清潔保持が主な目的です。それ以外にも、身体が温まり緊張がほぐれることでのリラックス効果も期待できます。また、適温での入浴は副交感神経が優位になり、気持ちよく入眠できるのも期待できます。
入浴は体力を使うため、健康状態のチェックも必須です。体温はもちろん、血圧の上昇・低下にも気を付けなければいけません。また、床が濡れているため、転倒などの危険も多く、危険を予測した介助が必要になります。
介助の内容4(歩行介助)
歩行介助でも、転倒などのリスクを予測した介助が必要になります。高齢者は何でもないような段差でのつまずきが多く、足元周辺の状況には絶えず気を配らなければいけません。また、歩行介助は入浴介助同様に、介助を受ける方の状態によっていくつかの種類に分かれます。
介助される方と向き合い、手を取って介助する「手引き歩行介助」。
杖を使用する方の脇の下と肘を支える「杖の歩行介助」。
歩行器を使用されている方の後方から、脇の下を支える「歩行器の方向介助」。
そのほかにも「階段の歩行介助」や「半身麻痺の患側からの歩行介助」などがあります。
介助の内容5(移乗介助)
移乗介助は、介助を受ける人を乗り物から移す介助を指します。例えば、車いすからトイレへ移ることが困難な方に対して、移乗介助が必要です。移乗介助では、介助を受ける人の自力を活かしながら、転落や転倒への注意が求められます。特に高齢の方は皮膚が脆弱になっているため、少しの接触で皮膚がはがれてしまいます。そのため、車いすのフットレストなどに、身体が触れない配慮が必要です。
介助の内容6(更衣介助)
更衣介助では、着脱しやすい衣服の選択が大切です。それと同時に、どの服を着るのか本人に自己決定してもらうことも重要です。更衣のさいにも、できるだけ自力で行えない部分への支援を意識します。また、拘縮や麻痺などがある場合は「脱健着患(だっけん・ちゃっかん)」を意識します。
※脱健着患とは「脱衣時は健康な方から衣服を脱ぎ、着衣時は拘縮や麻痺がある方から衣服を付ける」という介助法です。
更衣介助は、意外に事故が多いものです。特に拘縮のある方に無理に服を着せようとすると、皮膚がはがれたり、場合によっては骨折したりするので慎重な介助が求められます。
適切な介助の度合いを考えよう
介助するさいには、その人の自立状態の把握が重要です。本人自らできることまでも介助してしまうと、その人の持つ能力までが低下してしまいます。その結果、生活機能が低下してしまっては元も子もありません。また、自立度には以下のように段階があります。
自立:日常生活において、介助を必要としない状態です。ただし年齢と共に、転倒などの事故リスクは高くなるので、動作中は注意を払って見守りましょう。
部分介助:基本的なことは自分でできるが、部分的な介助が必要な状態です。例えば「入浴時の洗身などはできるが、手が上がらないため髪が洗えない」などは、部分介助が必要となります。
完全介助:自力では日常生活の動作が困難な状態で、介助者が全面的に介助する段階です。
しかし、介護の目的が自立支援を目指していることには変わりありません。完全介助の方でも、その人らしい生き方、その人のできることを探っていく姿勢は大切です。
【まとめ】適切な介助で、自立を目指す介護をしよう!
「介護」とは、一人で日常生活を送るのが困難な方に、日常生活全般を支援して自立を目指す行為を指します。そして「介助」とは、自立を目指す「介護」を実現する手段となるのです。
「介護」は主に身体介護と、生活援助があります。対して「介助」は以下の6つに分けられます。
・食事介助
・排泄介助
・入浴介助
・歩行介助
・移乗介助
・更衣介助
介助をするさいには、介助を受ける方の自立度の把握が大切です。介助が足りなければ、自立への道が遠のくどころか、事故リスクが上がってしまいます。また、過剰な介助も、本人の持つ能力の低下を引き起こします。どちらにしろ自立へ向けた支援とは言えません。どの程度の「介護」「介助」が必要か絶えず考え、自立への道を探る姿勢を忘れないようにしましょう。