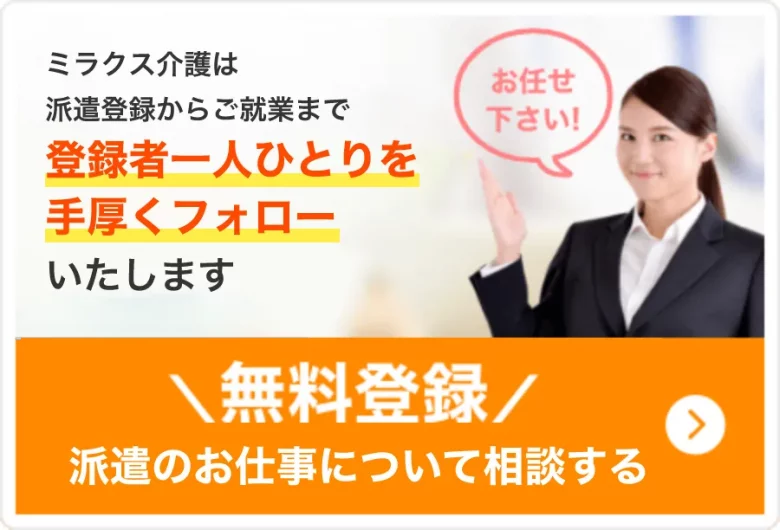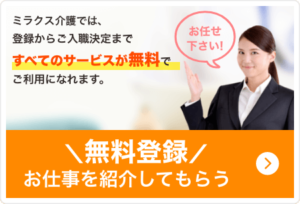移動介護従事者とは、視覚障害者・車椅子使用者・知的障害者の外出を支援する仕事です。「1人で外出できるようになりたい」と自立を目指す障害者の方から、外出の際に常に支援・援助が必要な障害者の方まで、様々な方の外出支援を行います。
本記事では、移動介護従事者の仕事内容と必要な資格についてご紹介します。
移動介護従事者とは?
移動介護従事者はガイドヘルパーとも呼ばれ、1人での外出が難しい障害者の外出や移動をサポートする職種です。
「全盲で1人での外出が不安だけど、いずれは1人で外出できるようになりたい」
「車椅子を使用していると、1人では登れない傾斜の強い坂道や、1人では進むのが難しい
砂利道があるため、移動を手助けしてほしい」
移動介護従事者は、このような障害者の方々の声に応えられるよう、サポートを行います。移動介護従事者がサポートを行う方は、視覚障害者や車椅子を使用する身体障害者、知的障害、精神障害者などです。ただ外出や移動の手助けを行うのではなく、障害のある方が1人で外出できるようになるための練習を行うことも移動介護従事者の役割です。
移動介護従事者の仕事内容
移動介護従事者は、どのような障害を持つ方を対象に、どのような手助け・サポートを行うのでしょうか。
ここでは、移動介護従事者の仕事内容を対象者別に3つご紹介します。
視覚障害がある方の外出・移動支援
弱視または全盲で、白杖や盲導犬を用いて外出・移動する方を対象に、外出や移動のサポートを行います。買い物や会計や必要に応じた代読・代筆など、目が見えないことで生じる外出時の不便さを解消することが移動介護従事者の主な役割です。
また、視覚障害のある方が1人で外出できるようになるために、買い物の仕方や公共交通機関の利用方法を一緒に練習することもあります。
全身性障害がある方の外出・移動支援
先天性筋ジストロフィーや筋萎縮性側索硬化症(ALS)など、全身性の障害により、車椅子を常時使用する方の外出や移動を手助けします。特に傾斜が強い坂道や砂利道、段差が多い歩道など、1人では移動しにくい道での介助・手助けを行うことが移動介護従事者の主な役割です。
知的障害・精神障害がある方の外出・移動支援
重度の知的障害や精神障害により、周囲の人とのコミュニケーションが難しい方の外出や移動を手助けします。重度の知的障害や精神障害がある方は、自分の想いが周囲の人に伝えられなかったり、場にそぐわない言動をとったりすることがあります。移動介護従事者は、知的障害・精神障害がある方の気持ちや考えをくみ取り、周囲の人との関わりやコミュニケーションの手助けをすることが主な役割です。
移動介護従事者に必要な資格・要件
移動介護従事者として働くためには、研修の受講が必要です。また、介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・介護福祉士など、高齢者介護に関する資格を持っている方が、スキルアップのために研修の受講をすることも可能です。
ここでは、移動介護従事者として働くために受講が必要な3つの研修をご紹介します。
同行援護従業者養成研修
同行援護従業者養成研修とは、視覚障害がある方の外出・移動支援に必要な知識が習得できる研修です。同行援護従業者養成研修には一般課程と応用課程の2つがあります。
・一般課程:視覚障害に関する基礎知識や支援技術を習得します
研修修了後は視覚障害者の同行援助を行う訪問介護事業所での就労が可能です
・応用課程:一般課程よりもさらに応用性の高い専門知識・支援技術を習得します
研修修了後は視覚障害者の同行援助を行う訪問介護事業所のサービス提供責任者として活躍することができます
同行援護従業者養成研修の一般課程・応用課程の各カリキュラムは以下の通りです。
【一般課程のカリキュラム】
| 科目 | 時間 |
| 視覚障害者福祉サービス | 1時間 |
| 同行援護の制度と従業者の業務 | 2時間 |
| 障害・疾病の理解① | 2時間 |
| 障害者の心理① | 1時間 |
| 情報支援と情報提供 | 2時間 |
| 代筆・代読の基礎知識 | 2時間 |
| 同行援護の基礎知識 | 2時間 |
| 基本技能(演習) | 4時間 |
| 基本技能(演習) | 4時間 |
| 計 | 20時間(約3日間) |
一般課程の受講要件は特に定められていません。
保持資格や職歴などの条件を問わず、誰でも受講することができます。
【応用課程のカリキュラム】
| 科目 | 時間 |
| 障害・疾病の理解②/td> | 1時間 |
| 障害者の心理② | 1時間 |
| 場面別基本技能(演習) | 3時間 |
| 場面別応用技能(演習) | 3時間 |
| 交通機関の利用(演習) | 4時間 |
| 計 | 12時間(約2日間) |
応用課程が受講できるのは、一般課程の修了者のみです。
応用課程の受講を希望する際は、先に一般課程を修了する必要があります。
全身性障害者ガイドヘルパー研修
全身性障害者ガイドヘルパー研修とは、全身に障害があり、車椅子を使用している方の外出・移動支援に必要な知識が習得できる研修です。研修修了後は、全身性障害がある方の同行援助を行う訪問介護事業所での就労が可能になります。
全身性障害者ガイドヘルパー研修の受講要件は都道府県によって異なるため、事前に各都道府県の受講機関に確認するようにしましょう。
全身性障害者ガイドヘルパー研修のカリキュラムは以下の通りです。
| 科目 | 時間 |
| ホームヘルプサービスに関する知識/td> | 3時間 |
| ガイドヘルパーの制度と業務 | 1時間 |
| 障害者福祉の制度とサービス | 2時間 |
| 障害者の心理 | 1時間 |
| 重度脳性まひ者等全身性障害者を介助する上での基礎知識 | 2時間 |
| 移動介助にあたっての一般的注意 | 3時間 |
| 移動介助の方法(演習) | 3時間 |
| 生活行為の介助(演習) | 1時間 |
| 計 | 16時間(約3日間) |
行動援護従業者養成研修
行動援護従業者養成研修とは、知的障害や精神障害がある方の外出・移動支援に必要な知識が習得できる研修です。研修修了後は、知的障害者・精神障害者の同行援助を行う訪問介護事業所での就労が可能になります。行動援護従業者養成研修の受講要件は特に定められておらず、保持資格や職歴など関係なく、誰でも受講することができます。
行動援護従業者養成研修のカリキュラムは以下の通りです。
| 科目 | 時間 |
| 強度行動障害がある者の基本的理解に関する講義/td> | 1.5時間 |
| 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識 | 3時間 |
| 強度行動障害のある者へのチーム支援 | 3時間 |
| 強度行動障害の生活の組み立て | 0.5時間 |
| 基本的な情報収集と記録等の共有(演習) | 1時間 |
| 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解(演習) | 3時間 |
| 行動障害の背景にある特性の理解(演習) | 3時間 |
| 生活行為の介助(演習) | 1.5時間 |
| 障害特性の理解とアセスメント(演習) | 3時間 |
| 環境調整による強度行動障害の支援(演習) | 3時間 |
| 記録に基づく支援の評価(演習) | 1.5時間 |
| 危機対応と虐待防止(演習) | 1時間 |
| 計 | 24時間 (約3~4日程度) |
移動介護従事者が活躍する職場
視覚障害や身体障害、知的障害、精神障害など、様々な障害を持つ方を対象に、外出・移動の手助けを行う移動介護従事者の仕事。移動介護従事者は、主にどんな職場で活躍しているのでしょうか。
移動介護従事者が活躍する職場は、以下の通りです。
・障害者へのガイドヘルプサービスを提供している訪問介護事業所
・障害者支援施設または障害者支援センター
・障害者向け共同生活援助施設(グループホーム)
・児童発達支援センターまたは放課後等デイサービス
移動介護従事者の仕事に向いている人の特徴
特定の研修を受講することで、移動介護従事者として働くことができます。しかし、移動介護従事者は利用者ごとに臨機応変な対応が求められるため、仕事の向き不向きには大きな個人差があります。
移動介護従事者の仕事に向いている人の特徴は、以下の通りです。
・コミュニケーション能力が高く、他者への興味関心が強い
・どんな状況や場面でも臨機応変に対応できる
・私生活でも外出や旅行が好きで、行動力がある
外出支援を通じて、障害者のQOL向上を
外出したいと強く希望していても、心身の障害により、思うように外出することが難しい方は大勢存在します。移動介護従事者は、障害がある方の外出や移動の支援を通じて、QOL(=生活の質)の向上を実現する職種です。移動介護従事者の仕事に興味がある方は是非、お住まいの都道府県が開講している研修の受講を検討してみてください。