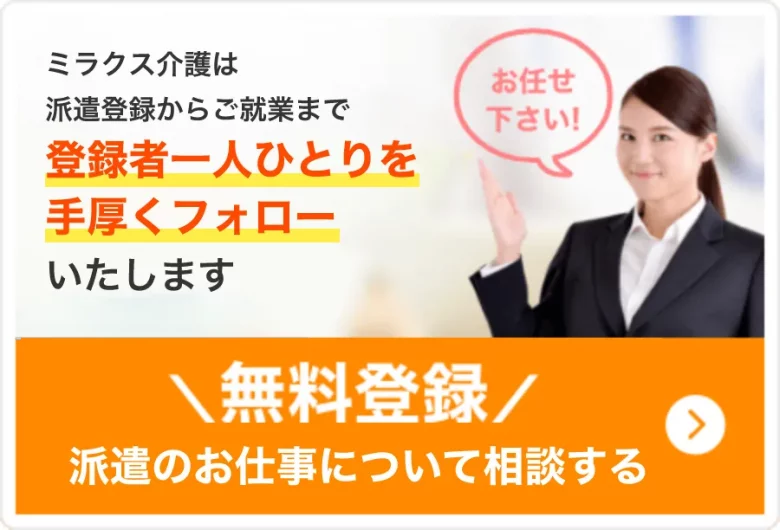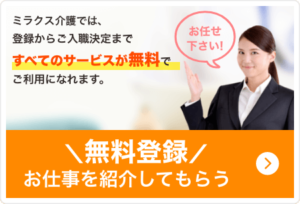脱健着患とは、片麻痺の方の着替えの介助を行う上で欠かせないキーワードです。「健側から脱ぐ」「患側から着る」という、介助の手順を示します。脱健着患の手順を守って介助することで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
本記事では、脱健着患で片麻痺の方の介助を行う意味やメリットについて解説します。
「脱健着患」とは?
「脱健着患」とは、脳梗塞や脳卒中などの脳血管障害による後遺症で、左右どちらかの手足に片麻痺がある方の着替え介助のポイントです。脱健着患は「健側(麻痺がない側)から脱ぐ」「患側(麻痺側)から着る」という介助の手順を指しています。脱健着患の手順で着替えの介助を行うことで、痛みや苦痛なくスムーズに衣服の着脱をすることができます。
なお、脱健着患で着替え介助を行うのは片麻痺の方だけではありません。手足の骨折や脱臼がある方に対しても、脱健着患を意識して着替えの介助を行います。
上着の着方・脱ぎ方
実際に「脱健着患」を意識して、片麻痺の方や手足に骨折・脱臼がある方の着替えの介助を行うには、どうすればいいのでしょうか。ここでは、脱健着患を活用した上着の着方・脱ぎ方の手順を解説します。
前開きの上着の着方・脱ぎ方
前開きの上着は、重度の片麻痺や骨折・脱臼により、腕の可動域に制限がある方に適しています。
着替えの際に腕に負担がかからないよう、脱健着患を意識して介助を行いましょう。
【着衣】
①椅子またはベッドに座ってもらう
着替えの介助を始める前に、まずは椅子やベッドに座ってもらいます。
この時、利用者の姿勢が安定していることを確認しましょう。
患側への傾きが見られる場合は、背もたれがついた椅子を用意してください。
介護者は基本的に、利用者の患側に立ちます。
②患側の腕を通す
上着のボタンを全て外したら、患側の袖を介護者の腕に通して引き抜き、袖を輪の状態にたくし上げます。
可能であれば、利用者に手渡し、自身で袖を通してもらいましよう。
③上着を背中に合わせる
患側の腕に上着の袖を通したら、上着を背中と肩に羽織ります。
腕の可動域に制限がある場合、自身で羽織るのが難しいため、介護者がサポートを行いましょう。
④健側の腕を通す
患側の袖と同様に、健側の袖を介護者の腕に通して引き抜き、袖を輪の状態にたくし上げます。
可能であれば、利用者に手渡し、自身で袖を通してもらいましょう。
⑤ボタンを留める
両方の袖が通せたら、ボタンを留めます。
可能であれば自身で留めてもらいますが、難しいようであれば介護者がサポートを行いましょう。
ボタンを留め終えたら、衣服のシワを整えましょう。
【脱衣】
①椅子またはベッドに座ってもらう
着替えの介助を始める前に、まずは椅子やベッドに座ってもらいます。
この時、利用者の姿勢が安定していることを確認しましょう。
患側への傾きが見られる場合は、背もたれがついた椅子を用意してください。
介護者は基本的に、利用者の患側に立ちます。
②ボタンを外す
上着のボタンを外します。
可能であれば自身で留めてもらいますが、難しいようであれば
介護者がサポートを行いましょう。
③健側の肩を外し、腕を抜く
健側の肩から上着を外し、健側の腕を抜いてもらいます。
肘を少し後ろに引いてもらうと腕が抜けやすくなります。
④患側の肩を外し、腕を抜く
健側の腕が抜けたら、次に患側の肩から上着を外します。
可能であれば、自身で健側の手を使って、患側の腕を抜いてもらいましょう。
かぶりの上着の着方・脱ぎ方
かぶりの上着は、ボタンやファスナーなどの付属品がないため着心地がよく、楽に着脱できることが特徴です。
しかし、肩関節・肘関節の動きに制限がある方には、あまり適していません。着替えの際に肩や肘の関節に負担がかからないよう、脱健着患を意識しましょう。
【着衣】
①椅子またはベッドに座ってもらう
着替えの介助を始める前に、まずは椅子やベッドに座ってもらいます。この時、利用者の姿勢が安定していることを確認しましょう。
患側への傾きが見られる場合は、背もたれがついた椅子を用意してください。
介護者は基本的に、利用者の患側に立ちます。
②患側の腕を通す
患側の袖を介護者の腕に通して引き抜き、袖を輪の状態にたくし上げます。
可能であれば、利用者に手渡し、自身で袖を通してもらいましよう。
③首を通す
患側の袖を通したら、肩まで引き上げ、そのまま首を通します。
可能であれば、健側の手で襟元を掴み、自身で首を通してもらいましょう。
④健側の腕を通す
首を通したら、次は健側の腕を通します。
可能であれば、自身で健側の腕を通してもらいましよう。
身頃を下まで下ろし、衣服のシワを整えます。
【脱衣】
①椅子またはベッドに座ってもらう
着替えの介助を始める前に、まずは椅子やベッドに座ってもらいます。
この時、利用者の姿勢が安定していることを確認しましょう。
患側への傾きが見られる場合は、背もたれがついた椅子を用意してください。
介護者は基本的に、利用者の患側に立ちます。
②健側の腕を抜く
上着の身頃を胸の上までたくし上げ、健側の袖から腕を抜きます。
③襟元から頭を抜く
健側の腕を抜いたら、襟元を持って襟元から頭を抜きます。
可能であれば、自身で健側の手を使って頭を抜いてもらいましょう。
④患側の腕を抜く
患側の袖から腕を抜きます。
可能であれば、自身で健側の手を使って患側の腕を抜いてもらいましょう。
ズボンの着方・脱ぎ方
ズボンの着脱は上着よりも身体のバランスが崩れやすく、転倒のリスクが高いです。
丁寧に声かけを行いながら、ゆっくりと介助を行いましょう。
ここでは、脱健着患を活用したズボンの着方・脱ぎ方の手順を解説します。
【着衣】
①椅子またはベッドに座ってもらう
着替えの介助を始める前に、まずは椅子やベッドに座ってもらいます。
この時、利用者の姿勢が安定していることを確認しましょう。
患側への傾きが見られる場合は、背もたれがついた椅子を用意してください。
介護者は基本的に、利用者の患側に立ちます。
②ズボンを患側の足に通す
患側のズボンの裾を介護者の腕に通し、裾を輪の状態にします。
そのまま、患側の足を軽く持ち上げ、介護者の腕から利用者の足にズボンを通します。
③ズボンを健側の足に通す
患側と同様に、健側のズボンの裾を介護者の腕に通し、輪の状態にした裾を健側の足に通します。
④ズボンを引き上げる
左右交互に利用者の臀部を浮かせながら、ズボンを腰まで引き上げます。
可能であれば、健側の手を使って自身でズボンを引き上げてもらいましょう。
なお、立位がとれるのであれば、ベッド柵や椅子の手すりを持って立ち上がってもらい、ズボンを腰まで引き上げます。
【脱衣】
①椅子またはベッドに座ってもらう
着替えの介助を始める前に、まずは椅子やベッドに座ってもらいます。
この時、利用者の姿勢が安定していることを確認しましょう。
患側への傾きが見られる場合は、背もたれが付いた椅子を用意してください。
介護者は基本的に、利用者の患側に立ちます。
②膝近くまでズボンを下ろす
左右交互に利用者の臀部を浮かせながら、膝近くまでズボンを下ろします。
立位がとれるのであれば、ベッド柵や椅子の手すりを持って立ち上がってもらい、ズボンを膝近くまで引き下げます。
③ズボンから健側の足を抜く
健側の膝を軽く曲げながら、ズボンから健側の足を抜きます。
④ズボンから患側の足を抜く
患側の足を持ち上げながら、ズボンから患側の足を抜きます。
可能であれば、健側の手を使って、自身で患側の足を抜いてもらいましょう。
脱健着患を行う際のポイント・注意点
脱健着患を行う際は、スムーズに介助が行えるよう、以下の点に注意・配慮しながら介助を進めることが大切です。
・季節問わず、着替えやすい室温(23~25℃)に設定する
・扉やカーテンを閉め、プライバシーを保護する
・脱いだ衣服につまづいて転倒しないよう、整理整頓する
・テープボタンやマグネットボタンなど、ボタンの付け外しがしやすい服を用意する
・動作ごとに1つ1つ、丁寧に声かけを行う
「脱健着患」で着替えの介助を行うメリット
片麻痺や骨折、脱臼がある方が、「脱健着患」で着替えの介助を行うことには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
着替えの介助で脱健着患を活用するメリットは、以下の通りです。
・介護をする側もされる側も、双方の負担を軽減できる
・患側を保護しながら、健側の動きを最大に活用できる
・患側への痛みや負担を最小限に抑えられる
スムーズに介助を行い、利用者の負担を軽減しよう
片麻痺や骨折、脱臼がある方の着替え介助では、「脱健着患」が欠かせません。脱健着患のコツや手順を理解すれば、スムーズに着替え介助が行えるため、介護をする側・される側、双方の負担が軽減できるでしょう。介護スキル向上のためにも、是非「脱健着患」の手順を覚えてみてください。