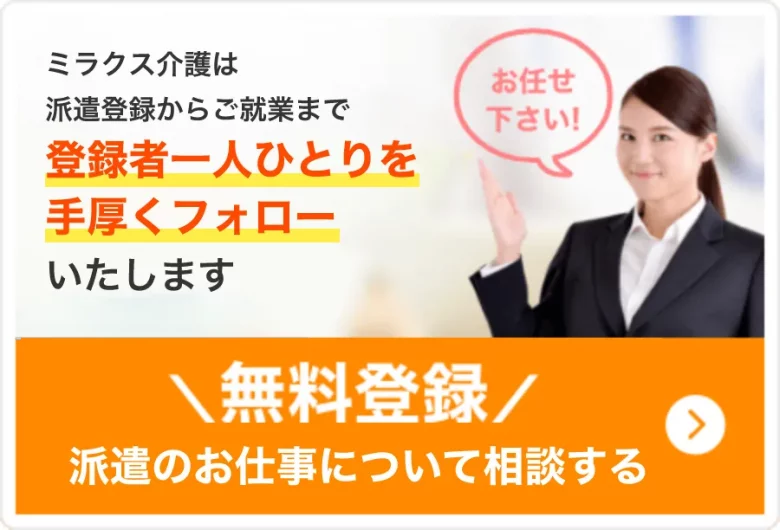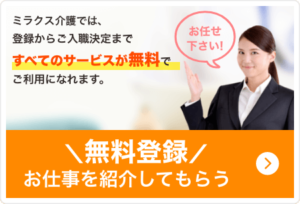社会福祉士の倫理綱領と言われても、あまりピンとこない方は多いのではないでしょうか。
社会福祉士がもつべき専門職としての価値観を示したものが、社会福祉士の倫理綱領です。ここでは、社会福祉士の倫理綱領の内容と重要性について解説します。
社会福祉士の倫理綱領とは?
社会福祉士の倫理綱領は、社会福祉士がもつべき価値観を示し、社会福祉士として活動するための行動指針として用いられています。
社会福祉士の倫理綱領は、1995年に日本社会福祉士会によって採択されました。その後も時代の変化に応じて改定を繰り返し、2020年6月に現在の倫理綱領が採択されています。
倫理綱領の内容
社会福祉士の倫理綱領は、「前文」、「原理」、「倫理基準」の3つの項目で構成されています。
2020年の改定前までは、「前文」、「価値と原則」、「倫理基準」の3項目でしたが、2020年の改定で「価値と原則」が「原理」へ名称変更されました。
各項目にはどんなことが書いてあるのでしょうか。次は、前文、原理、倫理基準それぞれの内容について解説していきます。
「前文」
社会福祉士の倫理綱領の前文では、社会福祉士は「人々がつながりを実感できる社会変革と社会的包摂の実現」を目指す専門職であるということを定めています。
前文の中でポイントとなるものが、「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」です。
ソーシャルワーク専門職のグローバル定義とは、ソーシャルワークを国際的に定義したもので、国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)と国際ソーシャルワーク学校連盟(IASSW)によって2014年につくられました。
社会福祉士の倫理綱領では、ソーシャルワーク実践の基盤としてソーシャルワーク専門職のグローバル定義を掲げ、社会福祉士の実践の拠り所として用いています。
ソーシャルワーク専門職のグローバル定義を理解することで、社会福祉士の倫理綱領をより深く理解することができるでしょう。
前文の次は、原理の項目に続きます。
6つ「原理」
倫理綱領では6つの原理を定めています。6つの原理は以下の通りです。
・人間の尊厳
・人権
・社会正義
・集団的責任
・多様性の尊重
・全人的存在
ひとつひとつ解説していきます。
人間の尊厳
社会福祉士の倫理綱領では、「人間の尊厳」を原理のひとつとして定めています。人間の尊厳とは、「すべての人間をかけがえのない存在として尊重する」ということです。社会福祉士の根幹をなす価値観が、人間の尊厳であると言えるでしょう。
社会福祉士が尊重すべき事項には、出自や人種、民族などが挙げられます。社会的な認識の変化により、2020年の改定で「性自認」「性的指向」といった性に関する事項が、新たに尊重すべき事項として追加となりました。
人権
社会福祉士の倫理綱領では、「人権」を原理のひとつとして定めています。
ソーシャルワーク専門職のグローバル定義の影響を受け、2020年に改定された倫理綱領には、新たにこの人権の項目が原理として加わりました。
人権とは、すべての人間が生まれながらにして持つ、侵してはならない権利です。社会福祉士は、いかなる理由でも人権の侵害を容認しません。
社会正義
社会福祉士の倫理綱領では、「社会正義」を原理のひとつとして定めています。
社会正義とは、社会的に正しい道理のことです。社会福祉士は、社会正義の実現を目指してソーシャルワークに取り組む必要があるでしょう。
差別や貧困、暴力など、社会正義を損なう要因はたくさんあります。2020年の倫理綱領の改定では、社会正義を損なう要因のひとつに「無関心」が追加されました。
集団的責任
社会福祉士の倫理綱領では、「集団的責任」を原理のひとつとして定めています。
集団的責任は、ソーシャルワーク専門職のグローバル定義の中に、新たな原則として加わりました。
それを踏まえ、2020年に改定された倫理綱領にも集団的責任が追加されています。
集団的責任とは、集団が人と環境それぞれに責任を持つことです。社会福祉士は、人と環境がお互いに協力し合う社会の実現を目指します。
多様性の尊重
社会福祉士の倫理綱領では、「多様性の尊重」を原理のひとつとして定めています。
多様性の尊重とは、一方的な価値観に偏らずにそれぞれの価値観を大切にするということです。
社会福祉士は、個人や家族、集団、地域社会にある多様性を理解し、それらを尊重する社会の実現を目指します。
全人的存在
社会福祉士の倫理綱領では、「全人的存在」を原理のひとつとして定めています。
全人的存在とは、人をひとつの側面から見るのではなく、生物的、心理的、社会的、文化的、スピリチュアルといったさまざま側面から見ることです。
社会福祉士は、すべての人々を全人的な存在として認識します。
以上が社会福祉士の倫理綱領で定めている6つの原理です。
原理の項目の次は、倫理基準の項目に続きます。
4つの「倫理基準」
社会福祉士の倫理綱領では、4つの倫理基準を定めています。4つの倫理基準は、以下の通りです。
・クライエントに対する倫理責任
・組織・職場に対する倫理責任
・社会に対する倫理責任
・専門職としての倫理責任
ひとつひとつ解説していきます。
クライエントに対する倫理責任
社会福祉士の倫理綱領では、「クライエントに対する倫理責任」を倫理基準のひとつとして定めています。
社会福祉士がソーシャルワークの実践を行ううえで、クライエントとの関わり方は非常に重要です。そこでこの項目では、社会福祉士のクライエントに対する倫理責任を12個定めています。
組織・職場に対する倫理責任
社会福祉士の倫理綱領では、「組織・職場に対する倫理責任」を倫理基準のひとつとして定めています。
社会福祉士がソーシャルワークの実践を行ううえで、クライエントの利益と所属機関の方針との間でジレンマを感じることは少なくありません。そこでこの項目では、社会福祉士が所属する組織や地域のネットワークに対する倫理責任を7個定めています。
社会に対する倫理責任
社会福祉士の倫理綱領では、「社会に対する倫理責任」を倫理基準のひとつとして定めています。
よりよい社会にするために働きかけることは、社会福祉士の役割のひとつです。そこでこの項目では、社会福祉士の社会に対する倫理責任を3個定めています。
専門職としての倫理責任
社会福祉士の倫理綱領では、「専門職としての倫理責任」を倫理基準のひとつとして定めています。
ソーシャルワークの専門職である社会福祉士は、その専門性を維持、向上することが欠かせません。そこでこの項目では、社会福祉士の専門職として求められる倫理責任を8個定めています。
以上が、社会福祉士の倫理綱領で定めている4つの倫理基準です。
ここまでは、社会福祉士の倫理綱領の内容について解説してきました。では次に、社会福祉士にとって倫理綱領はなぜ重要なのかを解説します。
倫理綱領はなぜ重要なのか?
社会福祉士にとって、なぜ倫理綱領は重要なのでしょうか。それは、この倫理綱領が社会福祉士にとって行動の規範になるからです。
ソーシャルワークを実践するうえで、多くの問題やジレンマが起こります。そんなときに、社会福祉士の判断や行動の拠り所となるのが倫理綱領です。
ソーシャルワークの実践で悩んだときには、この倫理綱領を読み返し基本に立ち戻ることで、ヒントや気づきを得られるでしょう。
まとめ
社会福祉士の倫理綱領について解説しました。
社会福祉士の倫理綱領は、社会福祉士の専門職としての価値観を示し、ソーシャルワークを実践するうえで欠かせないものです。判断や行動の拠り所として倫理綱領を活用することで、根拠に基づいたソーシャルワークが行えます。
社会福祉士の倫理綱領を理解し、ソーシャルワークの実践に活かしていきましょう。