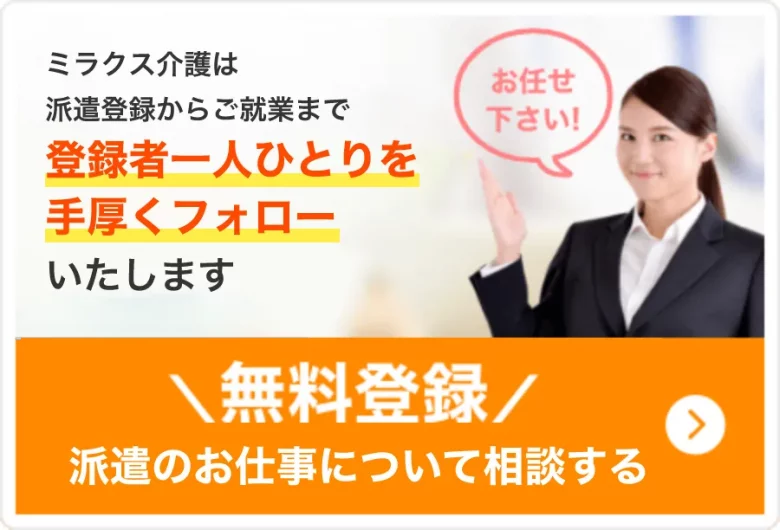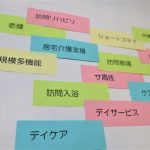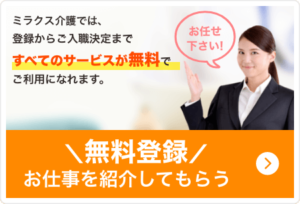確定申告をする上で出てくる医療費控除。会社員などで仕事をしていると、あまり馴染みのない医療費控除ですが、介護の仕事をしていると割とよく聞く言葉です。この医療費控除制度を、知っているのと知らないのとでは、負担する費用の面で大きな差が出てきます。今回は、この医療費控除制度を知らない人のために、シンプルに仕組みをお伝えする1記事です。
医療費控除とは
この章では医療費控除について触れていきたいと思います。
医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間で、本人もしくは扶養家族が支払った医療費が一定額を超えた時に受けられる控除のことです。支払った額に応じて、計算した金額を所得から差し引くことができるものです。
医療費控除の仕組みって?
医療費控除は、支払った医療費の額がそのまま戻ってくるというものではありません。1年間で支払った医療費に応じて、税金を計算し直すものです。 例えば会社員の場合ですと、医療費控除によって給与から天引きされた所得税の還付を受けることができます。また個人事業主の場合は、医療費控除を確定申告で申告する事により節税することができるのです。
医療費控除の対象になる費用
ここで、医療費控除とはどのような費用が控除の対象になるのかを、この章でお伝えしようと思います。
対象になる医療費
・病院での診療費/治療費/入院費
・医師等の送迎
・入院の際の部屋代や食事代の費用
・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
・治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
・通院に必要な交通費
・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
・子供の歯列矯正費用
・治療のためのリハビリ/マッサージ費用
・介護保険の対象となる介護費用
他に医療費控除になるもの
医療機関で支払った診察費や薬代には、保険外診療(保険適用外)の支出も含まれます。 例えば薬局で購入した風邪薬など、セルフメディケーション税制の対象となる一定の市販薬(OTC医薬品)も特例として医療費控除の対象となる場合があります。 しかし、気をつけて欲しいのが通常の医療費控除の適用を受ける場合、セルフメディケーション税制を受けることはできませんまた、治療費以外にも入院費や入院中の食事代が対象になったり、妊娠・出産にかかる定期健診、検査、入院、不妊治療費などもその中に含みます。
歯の治療だと、保険適用外の高価な材料を使用する場合も含まれます。入れ歯やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセン(セラミック)は一般的な歯科材料になります。そのため医療費控除の対象となるのです。さらに高価なインプラントですが、保険適用にはなりませんが、医療費控除では対象になります。 さらに歯列の矯正治療は、子供の嚙み合わせを矯正する目的で施術を受けた場合も対象です。その他にも、バスや電車などの公共交通機関を利用した医療機関、病院への交通費も対象です。タクシーは緊急性がある場合や電車やバスが利用できない場合に限り認められいます。申告の際に領収書を添付する必要があるので、もらったらしっかり確保しておいてください。
医療費控除の基準
結論から言うと、医療費控除は医療費の合計が10万円を超えると受けられます。これは総所得が、200万円超か200万円以下かによって変わります。総所得が200万円を超えている時は、医療費が10万円を超える分について医療費控除が可能です。また総所得が200万円以下の時は、10万円ではなく総所得の5%を超える分の医療費控除が受けられます。
医療費控除の計算式
ここで、医療費控除の対象となる金額の計算式をお伝えします。
【医療費控除額(上限200万円)=
医療費(保険金で補填された額を除く)- 10万円】
重複しますが、総所得が200万円以下の人は、10万円ではなく総所得の5%を超える分の医療費が控除なので気をつけてください。 もう一点注意点として、医療費控除の上限額は200万円です。覚えておいてください。
医療費控除の対象にならない費用は
この章では医療費控除の対象にならない費用についてご説明します。簡単に言うと、病気を予防するための医療費は医療費控除の対象外となっています。
以下が具体的な対象外のものです。
・美容整形、容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
・健康診断の費用
・タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除く)
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
・治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用
・親族に支払う療養上の世話の対価
・疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用(疾病を予防するための予防接種、サプリメント、漢方薬やビタミン剤等の費用を含む)
・親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼
・人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象)
・里帰り出産のための実家への交通費
・自分の都合で利用した差額ベッド代
・疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものの対価
医療費控除の申請方法
続いて医療費控除の申請方法についてご説明します。
医療費控除の申請手順
1. 医療費の通知や領収書で医療費控除の対象になるか確認
年間でかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えているかどうかを、医療費の通知や領収書で確認します。
2. 医療費控除と還付の金額を計算する
医療費控除の対象か確認したら、次に控除額と還付額の計算をします。
【医療費控除の計算式】
医療費控除額(最高200万円)=
(その年に支払った医療費の総額 – 保険金などで補てんされる金額) –
{10万円(所得の合計金が200万円未満の人は、所得の合計額の5%)}
【医療費控除の還付金の計算式】
還付金 =
医療費控除額10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)× 所得税率
3. 確定申告書と医療費控除の明細書を作成
税務署の窓口、もしくは国税庁のホームページから【確定申告書】や【医療費控除の明細書】を入手して作成。
4. 確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出
作成した【確定申告書】と【医療費控除の明細書】を税務署に提出。
5. 医療費控除で還付金をチェック
確定申告から約1ヶ月〜1ヶ月半後に、指定銀行口座に振り込まれるか、もしくは最寄りのゆうちょ銀行や郵便局で受け取れます。平成29年分の確定申告から医療費の領収書の提出は不要になりました。
しかしながら5年間の領収書保存と、医療費の領収書の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要です。 医療費控除の明細書は、税務署または国税庁のホームページ【医療費控除の明細書】からダウンロード可能です。
医療費控除申請時に必要な書類
医療費控除の申請で必要な書類は以下です。
・医療費控除の明細書
・確定申告書
・医療通知書
・本人確認書類
2023年提出分(2022年分)からの確定申告は確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bに統合された「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」を使用します。 なお、2021年以前の確定申告は、従来の確定申告書Aと確定申告書Bの書式で問題ありません。
領収書は5年保存
確定申告が終わってからも、5年間の保存義務があります。
なので領収書は大切に保管してください。
まとめ
筆者自身、医療費控除を調べることで知らなかったことや、学びを多く得ることができました。医療費控除を受けることで、ご自身の健康に惜しみなく投資できますし、通院しやすくなります。せっかくの国の制度です。しっかりと活用して、ご自身の生活に活かしてください。読んでいただきありがとうございました。